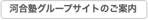脱炭素社会の流れで工場が閉鎖。その後の地域発展策を提言
~資料探しは図書館を活用、行政にもインタビュー
海城中学高等学校 高等学校2年 森下陽斗さん
公益財団法人図書館振興財団が主催する「図書館を使った調べる学習コンクール」。海城高等学校2年生の森下陽斗さんは、2023年(第27回)コンクール「高校生の部」に『地域衰退のない脱炭素の実現に向けて ~炭鉱閉山を教訓にして、公正な移行に必要な政策を提言~』で応募し、文部科学大臣賞に輝きました。
(2024年12月取材)

環境も経済も守る環境問題解決とは?
日本製鉄の高炉廃止を事例に
―まず、受賞した『地域衰退のない脱炭素の実現に向けて ~炭鉱閉山を教訓にして、公正な移行に必要な政策を提言~』のテーマを決めた理由と、調べ学習の概要を教えてください。
製油所の閉鎖により地域社会が衰退する雑誌の記事を読み、気になりました。理由を調べると、世界的な脱炭素の潮流が閉鎖の要因の1つであることがわかりました。そこで、脱炭素を実現しつつ、地域の雇用や経済を守る方策はないかと考えました。
具体的な事例としては、茨城県鹿嶋市にある日本製鉄㈱東日本製鉄所鹿島地区で、2基ある高炉のうち1基が2024年度末に廃止されることに着目し、廃炉後の地域の発展に向けた政策を提言することにしました。
提言に向けては、過去に学ぶことが大切だと考え、高度経済成長期の石炭から石油へのエネルギー転換にともなう炭鉱の閉山について調べました。具体的には、閉山後の地域経済発展に成功した常磐炭鉱と失敗した夕張炭鉱を取り上げて比較しました。
東日本製鉄所鹿島地区の高炉廃止については、鹿嶋市や市議会議員の方にインタビューをして現状をうかがいました。この過程で、製鉄ニーズの減少に伴う廃炉は、地域経済だけでなく製鉄技術の継承の面でも課題であることがわかり、新しい鉄の開発や賃貸工場としての活用といった具体策を提案しました。
―今回のテーマに問題意識をもったきっかけは何ですか。
直接的には、雑誌の『週刊東洋経済』で2023年に和歌山県有田市の製油工場が閉鎖されるという記事を読んだことです。記事では、閉鎖により有田市の地域経済が衰退する懸念が示されていました。そして工場閉鎖の理由を調べると、世界的な脱炭素の潮流が要因の1つであることがわかりました。
環境問題と経済の関係性について最初に興味を持ったのは、2020年7月に始まったレジ袋の有料化です。プラスチックゴミによる海洋汚染に焦点が当たっていましたが、私はそれと同時に「これまでレジ袋を作っていた工場はどうなっちゃうんだろう?」という疑問を持ちました。生計が成り立たなくなるかもしれない人を無視して断行するのは良くないのではという思いがありました。
もともと環境問題というと「重要な問題ではあるけれど、何となく綺麗事っぽい」というイメージが蔓延しているように感じていました。ですのでこの研究をしている間も、脱炭素を環境問題の文脈のみで語る見方を批判するスタンスでいました。調べていく過程で環境経済学の文献にも出会い、環境問題を、経済などいろいろな面と総合して考える学問があることを知りました。
―夕張炭鉱と常磐炭鉱閉鎖について調べたのはなぜですか。
脱炭素社会への公正な移行に関する先行研究を調べたところ、そのほとんどが海外で行われている成功事例で、日本も海外に見習うべきという論調で書かれていました。しかし成功失敗はあくまで現時点での話であって、数十年後にどうなるかはわかりません。一方、過去に日本が経験した炭鉱閉山なら、閉山・復興とその後の過程までを学ぶことができると考えたわけです。
閉山した炭鉱に夕張と常磐を選んだ理由は、どちらも観光事業で復興を目指したという共通点があり、成功要因と失敗要因を同じ項目で評価することができたためです。夕張が観光事業に失敗したのに対し、常磐は炭鉱閉山後、「常磐ハワイアンセンター(現・スパリゾート・ハワイアンズ)」による新産業創出の成功で知られています。
中学3年生の卒業論文発表で使用したパワーポイントより。常磐炭鉱と夕張炭鉱の閉山後の復興政策を比較したページ
製鉄技術の継承と新技術創出には、
新規参入のハードル低下が有効と考え提言
―提言の「賃貸工場」という案は、どのように出てきましたか。
鹿嶋市議会議員の方を取材したときに、「脱炭素による産業の将来性に対する不安から、製鉄に従事する人が減ったら製鉄技術が受け継がれなくなるかもしれない」と聞いて、「その問題を解決するには、製鉄にかかわる人を増やすのが一番だろう。それには、製鉄業に参入しやすい構造が必要だろう」と思いました。
そこで、提言の骨子は、「製鉄従事者の減少&製鉄技術の喪失の阻止→中小企業や個人が新規参入しやすい体制づくり→初期費用の節約→レンタル事業」といった感じで連想ゲームのように作っていきました。工業分野で設備をレンタルするという事例は少ないですが、現代社会でレンタルサービスは普及しているし、農業分野でもトラクターなどの大型設備を共同出資して購入するようなことは珍しいことではないので、それらの事例からヒントを得て考えました。