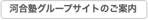少ない水で農作物を栽培するシステムを開発、「水のノーベル賞」ジュニア版の国際大会へ
青森県立名久井農業高校 環境システム科 3年 赤石紫音さん 白鳥滉弥さん
赤石紫音さんと白鳥滉弥さんは、高校の課題研究で、露地栽培や水耕栽培より使用する水量が大幅に節減できる「水を有効利用する節水型ミスト栽培システムの開発」に取り組みました。この研究で、ストックホルム国際水研究所によるストックホルム水大賞のジュニア版、ストックホルム青少年水大賞の日本大会で大賞を受賞し、スウェーデンで2024年8月に行われた国際大会に出場しました。
(2024年12月取材)

水槽の超音波ミスト発生装置を応用し
作物にミストで水分と栄養を供給
―まず、今回の研究に取り組んだ理由を教えてください。
赤石さん 地球は水の惑星と言われていますが、使える淡水はとても少なくて、農業がその貴重な淡水を最も多く使っています。そこで少ない水で農作物を栽培する方法を開発したいと考えました。
ミストを根にかける栽培法はすでにありますが、メンテナンスが大変など課題もあってまだあまり普及していません。そこでもっと簡単な方法はないかと考えて、水槽に酸素を送る超音波ミスト発生装置を使って栽培することにしました。
―どんな仕組みですか。
白鳥さん 作物の苗を、少しだけ養液が入った密閉容器に根が養液に浸からないように設置して、超音波ミスト発生装置で発生させた養液のミストを定期的に作物に供給します。密閉されているので養液の蒸発が抑えられ、露地栽培や水耕栽培より使用する水量が大幅に節減できるというものです。
―研究では、どのようなことを行いましたか。
赤石さん まずトマトで実験しました。トマトは水が不足すると実が腐るので、ミストの発生回数を変えて噴霧し、生育に最適な回数をみつけました。ただ、その回数だと水分が多くて糖度不足でした。そこで今度はミストを発生させる時間帯を変えて実験しました。
その結果、光合成が盛んに行われる日中に回数を増やし、夜間を減らしたところ、高糖度のトマトになりました。水は水耕栽培の約30%しか使いませんでした。超音波発生装置も少ない電力で稼働するので、省エネです。トマトのほか、レタス、スイスチャード、いんげんでも同じように実験しました。
―研究の手法や研究に関する知識は、どうやって学びましたか。
赤石さん 論文を読んだほか、名古屋市立大学の先生からは、根が吸えるミストの粒の大きさなどミストの特性について教えていただきました。また、根から短い根が生えたのですが、それが湿気中根であることを日本植物生理学会の先生に教えていただき、しっかり観察することにしました。


研究テーマは1人1つ持ちつつ、
お互いに協力し合う
―研究は授業で行ったとのことですが、どんな授業ですか。
白鳥さん 「課題研究」という授業で、週4時間あります。私たち「環境研究班」は、3年生7名、2年生3名で活動しています。同じ班といっても、研究は一人1つ持っていて、わからないことや困ったことがあると、皆で協力して解決します。そして誰かが大会などに出場することになると、他の人もその研究を手伝います。私も、赤石さんが国際大会に出ることが決まって、研究を手伝うことになりました。
赤石さん 私も装置からミストが漏れてしまったときには、みんなに協力してもらって改良しました。また、国内大会の際、審査員の方にデータが不足している点などを指摘していただいたので、国際大会に向けて、改めてデータを取り直すなど白鳥さんと二人で研究しました。

―ストックホルム青少年水大賞に応募したのはなぜですか。
赤石さん ストックホルム青少年水大賞は、水に関する研究であれば、応募することができます。「環境研究班」には、これまでも国内大会や、さらに世界大会に出場した先輩がいて、世界大会は私たちで5回目です。
―研究が評価されたわけですが、実用化されそうですか。
赤石さん 帰国してから、青森県内の農機具メーカーや県外の企業の方とお話しする機会がありました。実用化されるかどうかはわかりませんが、多くの人に使ってもらって、水の節約につながるといいと思います。
ストックホルムでは言葉の壁を実感
外国の生徒との交流は貴重な経験に
―ストックホルムはどうでしたか。
赤石さん 英語が苦手なので、コミュニケーションをとるのが大変でした。スマホの翻訳アプリを使えばだいじょうぶだろうと思っていましたが、十分ではありませんでした。
―他の国の若者との交流はいかがでしたか。
白鳥さん クイズやボーリング、パーティーをしたりして、楽しく過ごしました。ホテルは3人1部屋で、私はウクライナとイギリス代表の生徒と一緒でした。
赤石さん 私はキプロスとデンマークの生徒と一緒でした。

―今回の研究と経験を通して、勉強になったことはありますか。
白鳥さん 水質の分析をしたとき、手順をまちがえて何回かやりなおしたことや、実験に慣れたころに失敗したりしたことがありました。研究に限らず、何事もきちんと手順を追って丁寧にやらなければならないと思いました。
赤石さん ストックホルムで、言葉の壁を実感しました。同時に、コミュニケーションをとるのが難しい中でも、意見を交換するのが大事だとわかりました。
―最後に、卒業後の進路や夢について教えてください。
赤石さん 卒業後は理美容の道に進みますが、「水を大切に使う」など、この研究で学んだことを活かしていきたいと思います。
白鳥さん 私は福祉系の仕事に就く予定です。これまで取り組んできた研究は、自分でもできるので卒業後もやってみたいですし、良い栽培法が開発できたら、周りの人にも広めたいと思います。
―ありがとうございました。これからますますご活躍ください。