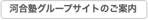脱炭素社会の流れで工場が閉鎖。その後の地域発展策を提言
~資料探しは図書館を活用、行政にもインタビュー
海城中学高等学校 高等学校2年 森下陽斗さん
(前回よりつづき)

調査では、多様な資料を幅広く活用
資料探しは図書館司書の協力が大きな力に
―調査にあたってはどんな資料を用いましたか。
主に図書館を活用して、書籍、雑誌、新聞、論文、ウェブサイト、関連企業や関連機関の経営計画、政府資料などを幅広く活用しました。
―使用した資料をどのように調べ、選びましたか?
資料探しは「広く浅く」を意識してとにかく多くの資料に当たりました。
また、私は先行研究を「あくまで自分のアイデアの説得力を肉付けするもの」として使うことを意識しました。先行研究の内容をそのまま論文に書こうとすると二番煎じになってしまうので、賃貸工場の例のようにまず連想ゲーム的に自分の構想を言語化した上で、その客観的根拠を求めて先行研究を調べました。その結果として、環境問題に関する文献にとどまらず、幅広い分野の文献に当たることができました。
資料検索では図書館の司書さんに協力してもらいました。図書館のコンピュータで検索をしても、なかなかぴったりの資料が出てこなかったのですが、司書さんに「こういうキーワードで検索してみたら」とか「こういう本もありますよ」などとアドバイスをいただいたことで思い通りの資料に出会うことができました。
―取材による調査もしましたが、どのように進めたのですか。
高炉閉鎖の新聞記事で取材を受けていた方で、日本製鉄社員で鹿嶋市議会議員の方に、私も取材させていただきました。また、行政側の意見も聞きたいと思い、鹿嶋市のホームページの問い合わせフォームからアポを取り、鹿嶋市の新事業担当の方に取材することができました。
炭鉱については、調べている過程で夕張市の石炭博物館の存在を知り、夕張市の復興事業の歴史に詳しい夕張市石炭博物館館長の方に取材しました。
環境問題の観点からの取材は、気候変動に関するNPO法人「気候ネットワーク」の方に対して行いました。気候ネットワークは「公正な移行」について提言している団体です。
4件の取材のうち、1件はメール、2件はZoomで行いました。鹿嶋市の市議会議員の方には対面で取材に協力していただきました。
―多様な資料を活用しましたが、メディアによる違いについてどう思いますか。
情報のリアルタイム度で言えば、新聞>論文>雑誌>書籍という感じがします。書籍や雑誌は内容は深いものが多いですが、すでに多くの人に注目されている話題になりやすいので、新しい学説や、特定の地域に絞った書籍というのは少ない気がします。その点、論文は地域研究も数多く出ているので役立ちました。
新聞記事はリアルタイムに物事を知るには一番ですが、分量が少なく、記者が取材した内容をそのまま伝えるので取材対象によって偏った意見になりやすいとも言えます。ゆえに新聞記事は世論を知る材料として利用する方が適切だと感じました。
取材は、これまで文字情報にされてこなかった当事者の本音を聞けるので貴重です。例えば、鹿嶋市議会議員の方への取材では、新聞記事に「高炉廃止強い危機感」とか「発表1ヶ月広がる不安」、「税収の見通し厳しく」と書いてあったので、私は鹿嶋市民の苦しい実情が聞けると思っていました。しかし、実際に取材してみるとそこまで逼迫していないという趣旨の回答を得たので拍子抜けしました。こういう情報は取材でしか得られないものだったと思います。
中学3年生の卒業論文発表で使用したパワーポイントより。多様な資料を用いて論拠を示した。写真は脱炭素の流れの影響を受けて車体に占める鉄の割合が低下してアルミニウムの割合が増加するという予測を示す資料(図1)と、精錬の際に消費する電力の比較から、製造時の二酸化炭素排出量は、鉄のほうがアルミニウムより少ないことを示す資料(図2)。
中学3年間の「社会科総合学習」で力をつけた
中高生は広く浅くテーマを設定するのがおすすめ
―それにしても、立派な論文を書き上げましたね。
海城中学高等学校は調べ学習が盛んで、「社会科総合学習」という授業で、中学1年生から中学3年生まで毎学期1テーマずつ個人で調べ学習をしてレポートを書くことになっています。3年生の論文はその集大成となります。その授業担当の先生にコンクールのことを教えてもらい、高1になって、国、地方自治体、市民のそれぞれがどのような姿勢で脱炭素に向き合っていくべきかについて指針を示すなど、論文をブラッシュアップして応募しました。
―「社会科総合学習」で、本格的な論文を執筆する力が身についたんですね。
これまでに貧困と教育の関係、アフリカのバッタ大量発生による食糧問題、群集なだれなどをテーマにレポートを書きました。中学3年生は、1万2千字〜2万字程度書きます。調査に取材を取り入れることも条件なので、校外の方に電話をかけたりメールを出したりする力もこの授業で鍛えられました。
―調べ学習をする中高生の皆さんにアドバイスがあればお願いします。
普通、論文は何かしらの新発見を発表するために書きます。しかし、大規模なアンケート調査などを行うことができる大人の研究と比べて、中高生の限られた研究環境で新発見をすることは容易ではありません。結果として過去の研究をかいつまんでまとめ直したような調べ学習にとどまってしまいがちです。中高生でも先行研究の二番煎じにならず独自性を出すためには、複数テーマの融合が最も簡単な方法だと私は思います。
私の場合、炭鉱閉山と脱炭素を融合させたわけですが、これは炭鉱閉山だけ、脱炭素だけを専門的に研究していたら得られなかった着眼点だったと思います。「狭く深く」の研究が難しいという中高生の方は「広く浅く」を目指すと独自性が出せるのではないでしょうか。
―最後に、大学では何を学びたいですか。
現時点では法学部に進学し、法律を用いて、社会問題を個人に寄り添って解決したいと思っています。社会問題には、経済、社会、人文などあらゆる分野からアプローチできますが、法学は、個人に焦点を当てて考えることもできる分野です。
今回の論文であれば、テーマは環境問題や地域経済といった比較的大規模な内容ですが、そこには地域住民や製鉄所で働く人がいます。閉鎖された炭鉱にも、そこで働く人や家族がいました。社会問題を個人というミクロな視点に立って考えていきたいと常々思っています。
―期待しています。本日はありがとうございました。