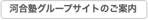全国生徒会大会2025 参加者に聞きました
実際に企画書を書く経験が、課題を深く考察するチカラにつながる!
坂田和真くん(穎明館高校[東京都]2年)
・学校の生徒会での役職:生徒会長
・参加回数:今回で3回目
◆参加したきっかけは?
初めて参加した際は、生徒会の先輩からの紹介でした。その先輩は以前から生徒会に携わっており、生徒会外務の顔としても他校の生徒会と交流を大切にしていました。その人から「この大会は絶対ためになる、役に立つ」と薦めてもらい参加を決意しました。
それまでは、このような大会に参加したことはなかったので、今でも誘ってくれたことを感謝しています。また、今振り返っても、自分が勇気を出して参加して良かったと思っています。
◆生徒会大会にいちばん期待していたことは?
普段聞くことができない他校の生徒会顧問の先生に意見や見解を聞くことができる点です。以前から、多摩生徒会協議会という地域の生徒会交流会に参加してきましたが、今回の大会のように他校の生徒会顧問の先生と議論ができる機会は、ここにしかないと思います。
顧問の先生方も、この大会や生徒から何か学びを得ようとしているため、とても有意義なお話をすることができました。生徒会は生徒と先生の板挟み的一面もありますので、先生側の視点を知ることはとても重要だと思います。
◆フェーズ2「立論」の議論のテーマは? 議論の中で難しかったこと・学んだことは?
「生徒会活動をどう引き継ぐか」をテーマに選びました。空想上の生徒会の想定課題として、生徒会で利用しているデジタルシステムが、現状は生徒会長のみ使いこなすことができる、という前提条件のもと、議論を始めました。
この学校の生徒会の問題点は、「生徒会活動の引き継ぎ」という重大任務を、会長ひとりで抱え込んでいることです。そのため、私たちのグループでは、引き継ぎ作業の分業が必要不可欠であると考えました。引き継ぎ任務は会長ひとりで行うのではなく、副会長をはじめ生徒会役員全体として行う必要がある、という共通認識をグループ内で共有することができました。
ただし、「引き継ぎは文字として文面だけを残すだけでは不十分である」という指摘が出たため、後輩には文面を残すことに加えて、実務経験を積むことの重要性を再認識しました。結論として、私たちの班では、生徒会役員全員で引き継ぎを行うこと、さらに文面だけでなく実際に経験を積むことを必須とすることが必須だと考えて、企画書を作成しました。
◆初対面のメンバーと議論したり、意見をまとめたりする際に、心がけたことは?
同じグループの参加者は、出身の都道府県が異なっていたり、男女別学など学校のシステムが様々だったりしたため、自分の認識と相手の常識は常に異なっていることを理解した上で議論を進めました。
◆「ココはびっくりした」と思ったことは?
全国からやる気に満ち熱心な生徒役員が集まっているため、自分のモチベーションもとても上がりました。
◆「これは自分の成長につながった!」と思ったことは?
全国生徒会大会2025企画の「『生徒会的』思考の訓練場」のフェーズでは、実際に企画書を書く機会があり、新たな学びになりました。
実際に企画書を書いたことで、課題を深く考察することができると感じたので、これから企画をする際には、ここまで深く考えることを心がけようと思うきっかけとなり、いい経験をすることができたと思いました。
◆全国の生徒会役員/今後役員を目指す人へのメッセージを!
迷っているなら絶対に参加する方がいいです。全国生徒会大会は、文字通り全国の生徒会役員が集まります。そして不思議なことに、解決したいと思っている学校や生徒会の悩みは、住んでいる地域は異なっていても、どの学校も似ています。
生徒会大会に参加することで、今まで面識がなかった人と友人になることができ、その仲間を活用して様々な情報を共有したり、知恵を集めたりすることで、問題を解決へと導くことができます。間違いなくいい経験をすることができますので、ぜひ次回の全国生徒会大会への参加を検討してみてください。