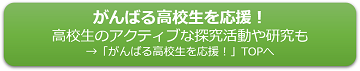かがわ総文祭2025
郷土芸能 伝承芸能部門
地元に伝わる「芸北神楽」。迫力ある「八岐大蛇」の演目で観客を魅了
広島県立加計高等学校芸北分校
芸北分校神楽部
3年 副部長 津守美和さん
演目:「八岐大蛇」
(2025年7月取材)

舞方、大蛇役、囃子方、裏方が力を合わせて舞台を作る
―今回の舞台で演じた伝統芸能と、演目について教えてください。
私たちの学校がある広島県の芸北地域には、郷土芸能の「芸北神楽」があり、数多くの神楽団があります。ちなみに神楽とは、神社のお祭りなどで神様に奉納される楽や舞などの芸能のことで、全国各地にそれぞれの土地ならではのものがあります。現在は、神社でのお祭りだけでなく、郷土芸能として、観光向けの公演や地域のイベントなど、さまざまな機会に上演されています。
「芸北神楽」は、「石見神楽」で有名な島根県の石見地方から伝わって、この地で独自に発展してきたものです。「芸北神楽」にはさまざまな演目があり、同じ演目名でも、神楽団によって独自の舞があります。今回演じた「八岐大蛇」は、古事記で有名な「八岐大蛇」が神楽化されたものです。
―今回の演目の特徴やみどころを教えてください。
舞方(まいかた)が細やかな所作(しょさ)で物語の場面を表現し、大蛇役(だいじゃやく)は神楽道具の中でもとても長く大きい「蛇胴」(じゃどう)を扱って、一頭一頭の動きと演舞でその恐ろしさを表現します。奏楽(そうがく)の囃子方(はやしかた)は魂を込めて奏で、裏方(うらかた)が幕裏で上演の動きや流れを支えています。3つの配役の力が合わさっての、幕前での元気が良く迫力のある演舞が見どころです。
―今回の演目はいつ頃から練習を始め、どんな練習をしてきましたか。
発表時間の13分間に合わせて動きや流れの構成を練りました。7月には他演目での舞台もあったので、いつ何の演目のどの場面をするのか時間を割り振って練習しました。本格的な練習は4月頃からになりましたが、やってみては何度も演技構成の練り直しや微調整をしました。
―今回の演目で、いちばん苦労したところを教えてください。
普段は約40分で演舞する壮大な演目を、どのように13分という限られた時間で表現し、伝えるのかというところに、とても苦戦しました。初めて神楽を観る人にもわかりやすく、物語の基本の「基」を外さずにできるかを大切に、話し合いを重ねて作り上げました。
―皆さんの演技のいちばんの魅力はどこにあると思いますか。
舞の美しさ!や細かい動きの丁寧さ!などと言いたいところですが…私たちはいつも“高校生らしさを大切に、元気100%以上の力で!!”という思いを大切にしています。高校生の私たちにしかできない“元気を与える神楽”が魅力です。

日頃は地元内外のイベント出演や交流、学校行事で上演。感謝を忘れず活動を続けたい
―普段の活動を教えてください。
お声をかけていただく県内のこども園や小学校、老人ホーム、地元のイベント、そして広島県高等学校郷土芸能大会など学校外での公演もあります。校内の国際交流などの行事でも公演しています。
―もはや部活を超えて、地元の伝統芸能を支える存在ですね。
部員の中には卒業後も神楽団に入って神楽を続けていく人もいます。神楽部としては、後輩たちにはこれからも芸北の神楽を受け継いでいってもらいたいです。また、神楽を捧げる神様、活動を支えてくださっている地域の方々への感謝を忘れず、「八岐大蛇」で言えば、新しい技や構成で会場をトリコにしてほしいです!
―最後に、総文祭の舞台に立った感想を教えてください。
本番当日のバスや控えの通路で「みんなガチガチに緊張して…」と想像していましたが、まさかの皆いつも通りに笑いながら楽しく話をしていてびっくりしました(笑)。さすがに本番5分前になると皆顔がひきつって緊張している様子でした。でも本番では、直前の緊張が嘘のように、いつも以上にかっこいい舞いや奏楽をすることができました。
入部してからこれまで、練習では一人一人の思いが強く、言い合いややる気がなくなることもありましたが、最後には今までで一番と思えるほどの拍手をいただくことができました。総文祭の日の拍手と舞台から見た景色は一生忘れません。