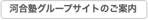かがわ総文祭2025
弁論部門
首のボルトと能登でのボランティアが「しぶとく生きること」を教えてくれた
千葉敬愛高等学校 弁論部
3年 橋口真翔(はしぐち まなと)さん
弁論タイトル:「だから、前を向く」
(2025年7月取材)

ピンチもチャンスも捉え方によって180度変わる
―今回弁論で訴えた内容を教えてください。
私の首の中にはボルトがあります。そのボルトのせいで私は夢であった野球や大好きだった運動をあきらめるほかなくなりました。しかし、このボルトは、高校で弁論という新たな道を切り拓くきっかけにもなりました。このボルトは私の絶望の象徴であると同時に、私の新たな第一歩を踏み出すきっかけとなったのです。幸運も不運も、ピンチもチャンスも捉え方によって180度変わる。悲観的な考えに陥りがちな日本人だからこそ、あらゆる社会問題や事柄を今までになかった新たな価値観で正面から見据え、しぶとく生き続けることが大切なのだと主張しました。
―特に強く訴えたかったことは何ですか。
どんな社会問題や困難にも新たな価値観で正面から向き合い、しぶとく生き続けることが大切なのだということです。これは首のボルトを通じて気付いたことでもあります。そしてこの発想こそが、たとえ私たちが絶望したとしても、心に光をともし、前を向かせてくれる力になると信じています。
―今回の弁論のテーマはどのように考えて決め、内容は、どのように構成しましたか。
私は弁論の原稿を書くとき、いつも聴く人に希望を与えられるようなものになることを心がけています。前を向いて生きていくことはこれから先も変わらず大切なことだと考えて、このテーマを決めました。
弁論の基本は自分の実体験をもとに原稿を書くことで、それが聴衆を説得する大きな力になります。そこで私は首のボルトのことと能登でのボランティアの経験を交えて書くことにしました。さらに、少子高齢化やセロトニン(※)といった、今注目されている社会的な話題も取り入れることで、より説得力がある原稿を仕上げることができました。
(※セロトニン:“幸せホルモン”と呼ばれる神経伝達物質)
災害大国日本では助け合いは欠かせない
―弁論にあたり、苦労したことはありますか。
一番苦労したのは表現の仕方です。強弱だけでなく緩急を自然につけて聴衆が聞き取りやすく、内容を理解してもらいやすくするために工夫しました。顧問の先生に表現の仕方の指導をしていただいたり、県大会のときに録音した自分の弁論に合わせて練習したりと、工夫して練習しました。
―総文祭には、なぜ出場することにしたのですか。
千葉県大会で最優秀賞をいただき、総合文化祭に出場することになりました。実は、1年生の時も岐阜で行われた総合文化祭に出場したのですが、その時は思うような結果を出すことができませんでした。今年の大会は私にとってリベンジのチャンスでもありました。その中で、総合文化祭で優良賞を獲得できたことは、とても光栄です。
―弁論で触れられていた、能登でのボランティア活動についてお教えください。
能登半島でのボランティアでは浜辺に流れ着いたごみの回収や被災者の方たちへの炊き出しなどを行いました。浜辺には、隆起によって新たなごつごつとした土地が形成されていました。そして炊き出しの際、能登半島の人々が助け合いながらしぶとく生きていらっしゃる姿が非常に印象的でした。中には家を失い、ビニールハウスで暮らしている方もいました。
活動中、ある被災者の男性が「みんなが助けに来てくれて本当に感謝している」とおっしゃっていました。こんな私でも、たとえ微力であっても人のためにできることがあるという大切なことに気付けた瞬間であり、日本人はこうして助け合いながら生きていると実感した瞬間でした。災害大国である日本に住む私たちにとって、助け合いは欠かせないものだと強く思います。

将来の夢は難民支援。まずは弁論で難民問題を社会に発信したい
―総文祭の感想を聞かせてください。
出場した弁士の主張を聴いている時が楽しかったです。多様性や手話、戦争、国際化など、様々なテーマが取り上げられていました。時には自分とは全く別の視点からの主張を聴くことができて、非常に有意義な時間でした。
他県の弁士と交流した時間も忘れられません。中には以前の大会で競い合った弁士もいて、お互いに自分の都道府県の魅力を紹介し合ったり、弁論部の練習について共有したりしました。
―今後取り組んでいきたいことや、将来の夢を教えてください。
生活に苦しむ難民のために尽くすことです。私は以前ドイツに住んでいました。日本とは違い、ドイツにはたくさんの難民が住んでいます。それは私がドイツの街を歩いていてもわかるくらいでした。
その経験を通じて、いつかドイツを中心とした、難民受け入れ国にいる難民を救いたいという思いが芽生えました。将来は、彼らに明日を生きる希望を与えるための活動をしたいと考えています。そのためには、まず多くの人が難民問題に関心を持ち、この問題に対して理解を深めることが必要です。私はこれからも弁論を続けて、この問題について社会に発信していきたいと考えています。