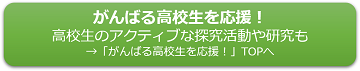かがわ総文祭2025
弁論部門
気仙沼の「森は海の恋人」活動に共感 「人々の心の森に木を植えること」を実践
長野県上伊那農業高等学校
3年 三池野生(みいけ ひろき)さん
弁論タイトル:「心の森 ~森は海の恋人~」
(2025年7月取材)

高校では里山コースに所属 森林環境について学ぶ
―まず、今回の弁論の内容を教えてください。
演題は「心の森 〜森は海の恋人〜」で、豊かな生態系を守る上で、自然の繋がりを意識し、子どもたちへの教育が最も必要であることを訴えました。
―その思いに至った経緯を教えてください。
まず、私が生まれ育った長野県下伊那郡大鹿村は村の97%が山林原野で、私も子どもの頃から森に慣れ親しんできました。しかし山師の父から森が荒れ始めていることを教えられ、森を守りたいと決心して、森林環境について学べる上伊那農業高校に進学することを決めました。
一方、中3の時、宮城県気仙沼市の漁師の方たちによる「森は海の恋人」運動を知りました。これは、赤潮の海に青さをとり戻すため、気仙沼に注ぐ川の上流部で落葉広葉樹を植林するというものです。
ところが2011年の3月11日、東日本大震災が発生し、気仙沼の海は壊滅的な打撃を受けました。しかし数年後には生態系が回復して、海に魚たちが戻ってきました。それは、震災後も続けてきた「森は海の恋人」運動の成果でもありました。私はこの活動に共感し、毎年、宮城県に行って植林活動に参加しています。
この活動の中心である、NPO法人「森は海の恋人」の理事長・畠山重篤さんは、子どもたちへの教育を重視していて、活動には地元の小学生もたくさん参加していました。畠山さんは、森と海の繋がりを次世代に伝えようとしていて、これを「人々の心の森に木を植えること」とおっしゃっていました。
―活動に感銘を受けたことが弁論につながったんですね。
はい。私は高2から里山コースに所属し、「ものづくりで森づくり」をテーマに、地域の森林資源を利活用しています。また、森への関心を高めてもらえるように、地元小学生や地域の方々との学習交流会を行って、「人々の心の森に木を植える」ことを実践しています。

総文祭出場では畠山さんの教えを伝える
―総文祭に出場しようと思ったのはなぜですか。
多くの人たちに森と海がつながっていることを発信できると思ったからです。また、今年の4月7日、畠山さんの訃報に触れました。まだ、教えていただきたいことが沢山ありました。私は、畠山さんに心の森に木を植えてもらった一人として、山の森、海の森、そして心の森の3つを大切にすることを伝えていきたいと思い、「人の心の森に木を植えること」こそが「森は海の恋人」の本質だと訴えることにしました。総文祭出場は、親孝行になると考えたこともあります。
―弁論の中では語りきれなかったけれど、同じ高校生に伝えたいことはありますか。
最初は、興味をもった「海は森の恋人」運動に長野県から遠く一人で参加するのはとても不安でした。でも、実際に訪れると多くの仲間との大切な出会いが生まれたことです。
―今回の発表で、苦労したことはありますか。
私は自分に甘い性格で、努力することが苦手でいつも逃げていました。でも、力の出し惜しみはもったいないと思い、腹をくくって頑張りました。
―最後に、総文祭の舞台に立った感想を教えてください。
新たな感覚に触れ、ワクワクさせられたことで、自分の価値観や考え方が豊かになったと思います。そして、他校の発表者の生き方に心を動かされました。