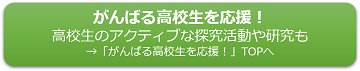かがわ総文祭
弁論部門
沖縄の「しまくとぅば(島言葉)」をはじめ、地域の言葉や文化を後世に
沖縄尚学高等学校
3年 兼謝名希実(かねじゃな のぞみ)さん
弁論タイトル:「つなぐ しまくとぅば(島言葉)」
(2025年7月取材)
ローカルを大事にしてこそ、グローバルな社会がある
―今回の弁論の内容を教えてください。
今回、「つなぐ しまくとぅば」という題で、地域に根付くローカルな言葉の大切さについて発表しました。私の住む沖縄県には島言葉(しまくとぅば)という古くからの言葉があるのですが、今ではあまり使われなくなってしまい、遂に平成21年ユネスコによって消滅の危機に瀕する言語に指定されました。沖縄に限らず地域の言葉や文化を継承していくという意識が私たちの生活の中で薄れつつあることに危機感を持ち、この現状について今一度多くの人に一緒に考えてもらいたいと思い、弁論の原稿を書くことにしました。
―何を最も強く訴えたかったですか。
今回の発表では、自分が生まれ育った土地に根付く言葉がいかに私たちの「こころ」となる大切なものであるのか、そしてこの広い世界はローカルの繋がりであり、ローカルを大事にしなければグローバルな社会は成り立たないということを強く訴えました。何気なく存在する地域特有の言葉は決して単なる言語ではなく、その地域の人たちの生活や文化と深い関係があり、かけがえのないものであるということを一人でも多くの人に知ってもらうことで、消滅危機に瀕する言語の状況が少しでも改善されたらいいなと感じています。

地域の言葉、音色でしか表現できない、地域の心
―発表の背景となった三線と島唄、しまくとぅばについて紹介してください。
私は幼稚園生の頃に、姉が琉球舞踊を習っていた影響で三線を始めました。踊りをやらないかと勧められたこともあったのですが、琉球舞踊を大きく支える歌三線の音色にとても魅力を感じ、三線を習うことしか頭にありませんでした。
沖縄の三線、島唄の魅力は温かみのある音色とそれにのせる歌の歌詞にあると感じています。沖縄の音楽は他とは違う音階を持ち、そのメロディーは三線の音色でしか表現しきることのできないものだと思います。私は以前、アルゼンチンの、沖縄から移民された方々やその子孫の方々が多く住んでいる地域に行ったことがあるのですが、そこでは沖縄のこころ(ちむぐるくる)を忘れないよう、沖縄の三線や踊りなどの文化が継承されていました。三線の音色は国境を越えてもどこにいても沖縄の人(うちなーんちゅ)の心に残るものであるところも、沖縄の三線、島唄の魅力であると思います。
そして、その歌三線、島唄を支えるものがしまくとぅばです。島歌はすべてしまくとぅばで歌われるため、しまくとぅばの意味を理解していなければ一つの曲として成立しないと私は考えています。一つ例を挙げると、「かなさん(かなさんどー)」という言葉は直訳すると「愛している」という意味ですが、「好き」や「かわいい」「愛おしい」など様々なニュアンスが含まれた最大限に愛を表現する沖縄の言葉です。私は沖縄に限らず、ローカルな言葉でしか表現しきることのできない微妙なニュアンスが存在すると感じていて、それを表現できるところがローカルな言葉の最大の魅力だと思います。
言語学者による調査やユネスコの報告などの根拠も示す
―弁論の構成は、どのようにして考えましたか。
自分の経験だけでなく科学的な根拠を用いることで、より説得力のある弁論になるように心がけました。沖縄の言葉だけでなく、どれほどの言語がこれから失われてしまうのかを示したユネスコの報告があったのでそれを用いたり、イタリアの言語学者が沖縄県で行った調査結果のデータを用いたりしました。それらを弁論に加えたことで、ローカルな言葉消滅に対する危機感が私だけのものではなく、数値として示される根拠のあるものだと伝えることができたと感じています。
―今回、総文祭に出ようと思った理由を教えてください。
私の住む読谷村でイタリアの言語学者の方によって行われた島くとぅばに関する調査があり、その結果報告会に行ったのが一つの大きなきっかけでした。そこで、「沖縄で島くとぅばを話す人は話さない人よりも幸福度が高い」という結果が出たという話を聞いたときに、ローカルの言葉に秘められたパワーやその重要性を感じました。
そこで沖縄の島くとぅばについて調べてみると、ユネスコにより消滅の危機に瀕する言語として指定されていることを知り、しまくとぅばを後世へ繋ぎ残していくために何ができるのか考えさせられました。そこで高校生の私にもできる一つの方法が弁論大会に出場して、一人でも多くの高校生、私と同じような若い世代の人たちにローカルな言葉の重要性について知ってもらうことだと思いました。弁論大会に参加した結果、沖縄県代表として総文祭に参加することになりました。

―今回の発表で、苦労したところを教えてください。
今回大変だったのは、弁論の構成や内容をわかりやすく書きあげることです。沖縄のしまくとぅばを始点に書いているのですが、沖縄に限らないどの地域でも普遍的であるということをちゃんと伝えなければ自分の語りで完結してしまうため、それを意識して話の流れを作り、内容を考えることが少し難しかったです。そこで、指導してくださった先生が貸してくださった本を参考にしたり、方言に関する論文やウェブサイトの記事を読んだりすることで、他の人の考えも取り入れ自分の考えを深めるようにしました。
他県の生徒との交流でより意義のある弁論大会に
―総文祭の舞台に立った感想を教えてください。
総文祭の舞台に立った時とても緊張していたのですが、簡単には立つことのできないとても貴重な舞台だったので、後悔のないようこれまで通り発表しようと思いました。全国から集まった高校生の前で弁論するのはこれまでの大会と異なり、緊張とともにやる気に満ち溢れていました。終わった後はもう少しうまく表現できていたかなぁ、など少し感じたところもあったのですが、良くも悪くもこれが今の自分の最大の力だったので、悔いはありません。
また、自分が舞台に立っているときは他の弁士の方々が真剣なまなざしで話を聴いてくれていたことがすごく嬉しく、感動しました。また、自分とは違う県、環境で生活する同じ高校生が日常の中で気づき、考えていることを知ることができたことはとてもいい経験となりました。
大会の中で他県の友達をたくさん作れたこともとてもいい思い出になりました。弁士全員の発表が終わった後に交流会があったのですが、その時に「あなたの発表超よかったー!」などとお互いに話したりしていて、発表するだけで終わる大会ではなく、他県の人たちと関り交流し、話し合うことでより意義のある弁論大会になるんだなとすごく感じました。
―今後の抱負を教えてください。
今回の大会を通して、より自分の弁論の内容を研磨し多くの人に聴いてもらいたいという気持ちが強まりました。今年高3なので総文祭に参加することはもうできませんが、他の機会を探して、ローカルな言葉の大切さをこれからも沖縄から発信していけたらいいなと感じています。将来は、国際機関に勤めたいと考えています。そこでは文化や言語の保護などに携わる仕事につき、自分の人生の目標を達成できるように頑張っていきたいです。
★兼謝名希実さんの過去のU-18島唄者コンテスト(沖縄県文化協会主催)の動画も見てみよう(YouTube)
◆第8回U-18島唄者コンテスト「石くびり」 最優秀賞 ※2024年
兼謝名さんの登場は1:47頃
以下は小4・小5のときの動画です。