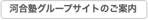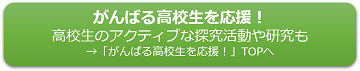あなたは音楽に命を懸けられますか ~芸術の深い理解へのいざない
ピアニスト 管谷怜子さん
10代といえば最も音楽に感化されやすい時期ですね。吹奏楽や合唱を通して、または個人的な活動を通して、音楽をする楽しみや喜びに目覚めて芸術の分野に進もうかなぁと思っている皆さんに、西洋音楽を中心に少しだけ美術を加えて芸術への理解を深めるための本をご紹介します。
天才たちの芸術とその歴史への想いがわかる本3選
歴史を踏まえない芸術など存在しない
(1)『西洋音楽史講義』(岡田暁生著)は、西洋音楽の始まりであるグレゴリオ聖歌から中世、ルネサンス、バロック、ウィーン古典派、ロマン派、印象派、近代、現代音楽、映画音楽までを簡潔に俯瞰することができます。今おなじみのゲーム音楽でさえ西洋音楽のルールに基づいて作られています。いきなりつまらない歴史のお勉強??と思った方、なぜ歴史を踏まえなければならないのか?という疑問にお答えしましょう!
音楽は芸術ですね。芸術は天才たちの長年にわたる知性と感性の高みにおいて時間をかけて育まれてきました(これを伝統といってもよいでしょう)。その時間の中に芸術はあります。要するにたった一人がぽっとでて、ベートーヴェンがあの音楽を作れたわけではなくて、バッハがいてハイドンがいてモーツァルトがいて初めてあの音楽が書けたのです。(この背景にピンとこない人は①を読んでください!)
歴史を踏まえない芸術など存在しないのです。河上徹太郎という20世紀の音楽評論家も「伝統のない所に芸術はなく、伝統は芸術の本質の一をなしている」と言っているので、私だけの妄言ではありません。

妥協なく難しいが、音楽を志すなら、生涯かけて読む本
そして天才ほどそのことを知っています。20世紀の指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1886~1954)も歴史的伝統の体現者・天才指揮者です。彼の著作(2)『音と言葉』(フルトヴェングラー著・芳賀檀訳)は、妥協なく難しい本です。哲学的で深くて重い。これは生涯かけて読み続けるべき本なので一読してわかる必要など全くないのです。2、3ページで投げ出しても良いので、音楽を志すならまず手元に置くことをお勧めします。
正直なところほんの一文を引用しても何も語ったことにならないくらい意味の深い文ですが、ベートーヴェンについて書いた部分を少し引用しましょう。
「このベートーヴェンの音楽の内心の緊迫の前に立っては、どんなによく練習をつんだ全音響芸術の文化をもってしても、手も足も出せぬ始末なのです。…」
あの『運命交響曲』の響きを紡ぎだす張本人が「手も足も出せぬ」と言っている、このベートーヴェンに捧げる敬愛には凄まじいものを感じます。翻訳した芳賀檀氏のあとがきに、フルトヴェングラーの『運命交響曲』演奏の後、「演奏が終わってもなお聴衆は感動して立ち去ろうとせず、ハンケチを振って一時間以上も別れを惜しんでいた」と書いています。その演奏にフルトヴェングラーの哲学的な思考による自己陶冶(とうや)が絶対不可欠であったことがわかるのです。

命を懸けて芸術に生きる宿命を引き受けた男
さて、天才ほど芸術に命を懸けるという厳しさを避けることはできません。常に自分の才能の限界を突き付けられているのが芸術家なのですから。そんな天才の宿命ということについて考えさせられる作品は、(3)『月と六ペンス』(サマセット・モーム著・金原瑞人訳)です。
画家の生涯を通して命を懸けて芸術に生きるという宿命を引き受けた男の話で、画家ポール・ゴーギャン(1848~1903)をモデルにしています。ゴーギャンといえば、35歳まで銀行マンだったのに急に画家を志し、ゴッホの親友だったのに仲たがいしてタヒチに楽園を求めた人です。「画家になりたいのではなく私は描かなければならないんだ」。ただこの一心で生きるのが芸術家なのだと思い知らされた作品でした。

もっと音楽や芸術を知りたい人へ
ベートーヴェンがもたらす強烈な音楽体験
(4)『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』(片山杜秀著)は、(1)に近い西洋音楽史の全貌を簡潔に解説した本です。ただベートーヴェンを「わかりやすい、うるさい、あたらしい」と平易な言葉で言い切ってしまうのは当たっていなくはないけれど、大胆過ぎないでしょうか。フルトヴェングラーが墓場から怒っている気がしますが(笑)。面白い切り口です。
(5)『フルトヴェングラーとカラヤン』(小川榮太郎著)は、前述したフルトヴェングラーとカラヤンという天才の生涯と西洋音楽の歴史伝統とその未来について、トスカニーニ、チェリビダッケ、バレンボイム、ティーレマンなどの指揮者の演奏批評を交えながら探求する本格的な作品です。音楽史がある程度把握できて、いろいろな演奏家の演奏に興味を持ったら必読の一冊でしょう。
ベートーヴェンに関する記述を引用しましょう。「ベートーヴェンの音楽が集中した聴取に値する強烈なコンサート体験を、初めて齎(もたら)した…」
この一言に私は一寸の疑いを抱くことすらできません。芸術とは、この雷に打たれるような恍惚の体験と精神の集中がすべてなのです。しかもこれは堅苦しいお勉強でも強制された優等生的な趣味でもなく、とても有意義で豊かな充実を人生にもたらしてくれるのです。

芸術家の宿命について考えさせられるゴッホの言葉
(6)『ゴッホの手紙』(小林秀雄著)も芸術家という人生を知るうえで外せません。③はゴーギャンをモデルにした物語ですが、こちらはゴッホの実際書いた言葉から芸術家という宿命について考えさせられます。
なぜ現在も人々はゴッホの絵に感動するのか、不思議に思ったことはありませんか。単に絵がうまいからでしょうか。ゴッホよりうまい画家はたくさんいます。ではなぜ??
それを小林秀雄は「質問の力」といっています。ゴッホは弟への手紙に「タッチとは、絵筆のひと刷毛とはなんと奇妙なものだろう」と書いています。この「感動という形で提出された質問」こそが、我々に強烈に訴えてくるものの正体ではないかと言っているのです。
また、ゴッホは精神を病んで自殺(一応自殺とされているが不可解な死でした)したのですが、その病気が精神分裂症か、てんかんかといった研究は、「これによってゴッホの芸術の理解を深めるという方向をとらないものなら、意味のない仕事でありましょう」と言っています。ここに、小林秀雄のぬくもりある眼差しが敬愛の念をもってゴッホをとらえているのが伝わってきます。

奥深く味わい深い芸術、ピアノ音楽
次にご紹介する本はもう絶版になって図書館や古本でしか手に入れることはできないかもしれませんが、(7)『世界の名ピアニスト』(小石忠雄著)は31人のピアニストを取り上げてその演奏と人生についてまとめられています。評論する日本語の美しさにも注目です。
さて、(7)のピアニスト論でも取り上げられた伝説的ピアニスト、ウラディミール・ホロヴィッツ。彼はピアノという楽器に特別のこだわりを持っていました。そのホロヴィッツが最も愛したピアノはなんと、日本にあるのです!
(8)『ホロヴィッツ・ピアノの秘密』(高木裕著)では、そのピアノの秘密、調律師という仕事について知識を得るだけではなく、ピアノ音楽とはいったいどうあるべきなのか?という原点に立ち返らせてくれます。この本の後、また(7)の本に取り上げられている歴史的巨匠たちの演奏を聴くと、ピアノの音色が実にバラエティに富み、ピアノ音楽がとても奥が深く味わい深い芸術であることが迫ってくるのです。まさに音と言葉の往復!! そこで(2)『音と言葉』の哲学的な文章に、ふたたび惹き込まれてゆきます。

芸術の道は険しいが、芸術には携われる
さて、これまでかなりマニアックな8冊の本をご紹介しました。難しい本も含まれています。しかも本にはそれぞれに「出会い時」という最適なタイミングがあります。皆さんの人生の中でその本に出会う最適なタイミングで、これぞ!と胸を張れる座右の書を見つけてください。
すべての分野に共通して芸術の道もまた険しいのは事実です。優しい大人はその事実を上手に隠しますが、早く知っておいたほうが良いでしょう。ただし、才能がなくても芸術に携われる可能性はあります。必須なものは何だと思いますか。それはひとこと、「芸術に対する敬愛」です。それを感じてほしくてこの8冊を紹介したようなものですから。
さて、あなたは何に命を懸けて生きてゆきますか?

[プロフィール]
管谷 怜子(すがや りょうこ)
福岡市出身。桐朋学園大学、同大学院大学修了。世界的ピアニストである故野島稔氏に師事し研鑽を積む。2007年FFGホール(福岡銀行本店ホール)にてソロデビュー。2023年、東京Hakujuホールのリサイタルなどで東京デビュー。2024年3月にリリースしたファーストアルバム「”《1853》ピアノソナタの黄昏”~リスト「ロ短調ソナタ」、ブラームス「ヘ短調ソナタ」(T&Kエンタテインメント)」は、雑誌「音楽現代」の推薦盤に選ばれる。2025年2月にはセカンドアルバム「”ベートーヴェン巡礼2027 Vol.1“~三大ピアノソナタ「月光」「悲愴」「熱情」(同社)」がリリース、同三大ソナタ含むコンサートが、5月29日、東京Hakujuホールにて開催予定。
https://ryoko-sugaya.com/concert.html