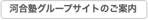近代とは? その成因を捉え直し、近代の苦悩の舞台、アフリカの今を知ろう
福田邦夫先生 元明治大学商学部教授 専門:国際貿易論
今の世界は、ピューリタン革命や勤勉さ・禁欲さではなく、奴隷制が作った
今の時代は、ポスト近代、第4次産業革命にあるなどと言われもします。しかし、世界の基本的なシステムは、やはり近代で、資本主義です。それにより様々な課題を抱えています。
近代史上、最大の出来事はイギリスにおける産業革命です。イギリスにおける産業革命を起点として資本主義社会が成立しました。産業革命を可能にした要因は何でしょうか。当時は(そして今も)、産業革命はピューリタンの勤勉と禁欲、節約、そして合理的精神が生み出した、という考え方が一般的でした。
本当にピューリタンの精神が優れていたからなのでしょうか。しかし産業革命が成立するためには膨大な資金(資本)が必要とされます。では産業革命に必要とするとされる資金(起爆剤)はどのようにして調達されたのでしょうか。
産業革命は、「アフリカ人奴隷の汗と血」の結晶
こうした疑問に対して、『資本主義と奴隷制』の著者・ウイリアムズは、西大西洋の奴隷貿易や新大陸のプランテーションで奴隷が果たした役割に着目し、奴隷貿易によって蓄積された莫大な利益が産業革命の起爆剤になったこと。そしてイギリス産業革命は、「アフリカ人奴隷の汗と血」の結晶でしかないという結論に達しました。
彼は研究成果を書き上げ、オックスフォード大学から博士号を授けられました。ウイリアムズは、新しい歴史の見方すなわちヨーロッパの歴史をアフリカ、カリブ海の歴史と結びつけたグローバルな考え方を提起しています。
彼は1911年にカリブ海のトリニダート島で生まれ、奨学金を得てオックスフォード大学に進学しました。ウイリアムズは、当時イギリスの植民地であったトリニダート島の独立運動の指導者としても活躍し、同島が独立した1962年にはトリニダート・ドバゴの初代首相に就任しました。

ヨーロッパ中心主義には根拠がない
『奴隷船の世界史』は、大西洋奴隷貿易が始まる15世紀以前の中世後期(12~15世紀)に地中海世界において奴隷制と奴隷貿易が存在していたこと。また大西洋奴隷貿易の先駆者としてのポルトガルの功罪についても、わりやすく説明してくれます。そして、15世紀後半から19世紀半ばまでの約400年にわたって1200万人ものアフリカ先住民が奴隷商人により新大陸に運ばれた歴史を明らかにしています。
また25年5月に文庫として刊行されることが予定されている『グローバル経済の誕生』は、グローバル経済とは何か、またグローバル経済はどのようにして形成されたのかということに関する様々な考えを検討し、ヨーロッパ人こそが歴史の原動力であるとするヨーロッパ中心主義には根拠がない。そうではなくて、非ヨーロッパ人こそが世界経済を形成するうえで決定的な役割を果たしたということを歴史的事実をあげて証明しています。
そしてヨーロッパ人は暴力を行使することによって、あるいは運によって歴史に登場したのであり、18世紀になってから優れたテクノロジーを持つようになったのであり、最初からヨーロッパ人だけが旺盛な起業家精神を持ち、また社会的適応性を持っていたという考え方に対して疑問を呈しています。
すなわち、近代資本主義社会の経済的基盤が、勤勉や節約によって築かれたのではなく、暴力や略奪によってもたらされたものであると主張しています。


コンゴから考えよう〜アフリカにこそ、近代の矛盾と苦悩が集結している
そして今、その近代にあって最大の苦悩はどこにあるのでしょうか。それは、近代が奴隷制との関わりもあったように、アフリカではないのでしょうか。
日本にいるとアフリカ大陸で日々起っている出来事に関する情報はほどんど伝わってきません。地理的に離れているからなのでしょうか。
アフリカ大陸は世界の陸地面積の4分の1を占め、人口は世界の約18%(14億人)を占めています。世界には「後発発展途上国」と命名される貧しい国が43か国ありますが、そのうちアフリカ大陸には33か国もあります。アフリカ大陸は、悲惨な紛争や飢餓、難民問題を抱えています。
コンゴの今を知る日本人著書による名著
『ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ?』の著者・小川真吾さんは、ウガンダやコンゴ民主共和国で紛争の犠牲になった人々の生活自立を支援するための活動に20年近く携わっています。アフリカ東部には豊富な地下天然資源があるのになぜ紛争が絶えないのか。こうした疑問に答えてくれます。
『世界最悪の紛争「コンゴ」』の著者・米川正子さんは破格の行動力のある優秀な研究者(現在神戸女学院大学国際学部)です。著者は国連平和維持軍に参加した経験を踏まえ、平和以外には何でもあるコンゴについて、報道されない歴史的現実を説明してくれます。
アフリカこそ研究してほしい分野
ベルギーの旧植民地コンゴ民主共和国は、われわれの日常生活には欠かすことのできないスマホやパソコンに必要なの電池の原料になるタンタルやコバルトの宝庫です。豊かな社会の豊かな人々の生活必需品であるパソコンやスマホを製造するためにはなくてはならない原料です。
コンゴ民主共和国では、独立した1960年から現在までの期間に800万人以上の人々が紛争の犠牲になっています。著者は1994年にルワンダにおいて2か月余りの間にフツ族とツチ族の対立により100万人もの人々が虐殺された事件についても触れています。アメリカや日本のような支配する国の立場から世界を見るのではなく、抑圧されてきた側、すなわち弱者の立場から世界を見ることの重要性に気付かせてくれる名著です。
アフリカはあまり研究されていない分野です。しかしアフリカこそ知っていただき、研究してほしい地域であり分野です。
もっと今の世界を理解するために触れてほしい本
実は大航海時代から続く、移民や難民、そして奴隷などの制度の上に、今の近代世界やアフリカの不幸があるかもしれないのです。そんなことを感じていただける代表的な本は、ほかにもあります。

『インディアスの破壊についての簡潔な報告』
ラス・カサス 染田秀藤:訳(岩波文庫)
クリストファー・コロンブスが「新大陸」を「発見」したのは、1492年。コロンブスの西インド諸島発見を契機として一攫千金を目指すコンキスタドーレスといわれる征服者がスペインから中南米やカリブ海に渡り、アステカやインカ帝国を滅ぼして支配下に置きました。
ラス・カサスは先住民を改宗させるために征服者と共に伝道師士として新大陸に渡りました。だがそこで目撃したのは残酷極まりない征服戦争でした。彼は余りにも凄惨な征服戦争に衝撃を受けて、カルロス一世国王に先住民の虐殺と征服戦争を止めるように訴えたのがこの報告者です。「太陽の沈まない国」とまで言われたスペイン帝国を支えたのがポトシの銀でした。
[出版社のサイトへ]

『奴隷制の歴史』
ブレンダ・E・ステイーヴンソン、所康弘:訳(ちくま学芸文庫)
『奴隷制の歴史』は、古代世界における奴隷制の歴史から、南北戦争を経て奴隷制が廃止されるまでの歴史について書かれた名著です。この本では、アフリカ大陸が新世界に対する奴隷供給源となった歴史的背景に焦点が当てられています。
15世紀後半から19世紀半ばまで約400年にわたって、1000~1500万人ものアフリカ先住民がイギリス、スペイン、フランス、オランダの奴隷貿易商人によって強制的にカリブ海や北アメリカに運ばれ、厳しい労働に従事させられました。本書では、合衆国が発展する中で奴隷が酷使され、搾取されてきた歴史が克明に書かれています。
[出版社のサイトへ]

『闇の奥』
ジョセフ・コンラッド、中野好夫:訳(岩波文庫)
この作品の舞台は、現在も紛争が絶えないコンゴ民主共和国(以下コンゴとします)です。紛争の主因はこの国の地下に眠っているコバルトやタンタル鉱石です。作者は青年時代、パリにあった「コンゴ上流開発会社」の船長として過ごし、その体験を小説に仕上げたのがこの本です。
当時コンゴは、ベルギー国王レオポルド二世の私有地であり、象牙の採集場でした。本書は反植民地主義を掲げて書かれた作品ではありませんが、アマゾン川に次ぐ世界最大・最長のコンゴ川の奥深い場所(闇)で繰り広げられた人間模様を見事に描写しています。
[出版社のサイトへ]

『共産党宣言』
カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス 大内兵衛、向坂逸郎:訳(岩波文庫)
この本は、1847年に書かれ、全世界の労働者に資本家による搾取のくびきを断ち切れと呼びかけています。確かにロシアをはじめ東欧諸国や中国で社会主義革命が成功し、社会主義国が成立しました。しかし1989年にベルリンの壁の崩壊に引き続き社会主義国家は崩壊し、残っているのは中国だけです。でも果たして中国は社会主義国家でしょうか。
『共産党宣言』は、社会主義国家論ではありません。そうではなくて資本主義社会の歴史的本質を抉り出し、数々の問題点を指摘しています。
[出版社のサイトへ]

[プロフィール]
福田邦夫
明治大学では、軍縮平和研究所の所長や、アフリカ文庫選定委員会委員長などを歴任し、リビアの大統領であったカダフィー大佐と明治大生との対話も実現してきた。「貿易論」は数百人集める明治大きっての人気授業だった。また筑摩書房がかつて推進してきた「ちくま大学」の開校でも大きな役割を果たした。