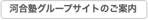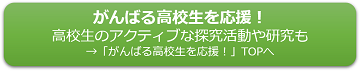防災・復興と地域活性化を研究・探究してみよう!
能登の未来を考えることは、すべての地方の未来を考えること。その参考やヒントになる本を、最前線の防災工学者が贈る 〈1〉
信岡尚道先生 金沢大学 能登里山里海未来創造センター
※元茨城大学 (2025年4月1日より、能登半島のある石川県金沢市に引越し、復興支援を行います。)
私は、土木工学を専門としています。土木工学は、道路や橋など大規模構造物の構造や、それが立つ地盤などを研究し、人の暮らしをサポートする分野です。2011年、東日本大震災のときには、津波のシミュレーションを皮切りに、地域復興や被災者の心の問題も調査対象としてきました。
2024年1月には、再び大きな災害、能登半島地震が起き、同年9月には大きな水害にも見舞われました。能登は、江戸時代の海運で栄えてきた歴史を持ち、文化的な魅力があります。一方、過疎の問題も抱えています。防災・復興・過疎化対策・学びの改革・心と福祉の問題など様々な課題が突きつけられています。
それらの課題に対して、様々な学問から挑もうとしています。また、防災、地域活性、コミュニティの再生などの課題に対しては、高校生のみなさんにも実践的な学び、探究的な学びを通じて挑むことができるはずです。
その一助になればと考え、私が作成してきた高校生にも使ってほしい本のリスト(一部ネット上のコンテンツ)を紹介します。探究活動だけではなく、進路選択の参考にもしていただけたらうれしいです。
Mw7.5の衝撃・能登半島地震および豪雨災害
能登半島地震はモーメントマグニチュードでMw7.5(断層地震として大きかった1995年の阪神淡路大震災はMw6.9)、とても大きな地震であり、能登半島全体と広範囲で強い揺れに見舞われました。このような大きな地震、強い揺れが過疎化の進む広い地域で発生したことは、これまでにありませんでした。さらに地震から10カ月たたない9月には、線状降水帯による豪雨が発生し、複合災害として能登半島を襲いました。これにより復旧はさらに大変になり、復興を遠ざけました。この地震と豪雨による複合災害について、課題を大きくわけると次の3つとなります。
A. 断層型巨大地震の解明および日本列島や日本海の形成との関係の把握
B. 過疎地域での巨大地震および豪雨による複合災害によるによる被害の特長
C. 日本の各地方での道しるべとなる能登半島の復旧・復興
能登半島は、世界農業遺産「能登の里山里海」があり、自然と人々の営みが調和した世界的に価値がある場所です。輪島塗の漆器は能登半島の輪島市で生産されていますが、その地では縄文時代から漆器が作られていたところです。
能登半島の復興の大きな計画として石川県は創造的復興プランを公表しました。この復興プランもみつつ、能登半島の災害からの復興、人口減少で高齢化の地方の未来への課題・視点を、さらに13項目にわけてみていきましょう。
関連サイト
【13の課題・視点】
1(A-1).断層型巨大地震である能登半島地震の特長
2(A-2).豪雨の中でも恐ろしい線状降水帯
3(B-1).能登半島における被害の特長(全般)
4(B-2).能登半島における被害と災害対応(建築物、社会インフラ)
5(B-3).能登半島や近年の災害における被害と災害対応(被災者支援)
6(B-4).能登半島や近年に災害における被害と災害対応(災害弱者・医療、心のケア)
7(B-5).能登半島における被害と災害対応(政治)
8(C-1).令和6年能登半島地震からの社会インフラの復旧
9(C-2).能登半島の復興へ(能登の魅力)
10(C-3).能登半島の復興へ(中越地震からの復興を学ぶ)
11(C-4).令和6年能登半島の復興へ(関係人口・二拠点居住)
12(C-5).令和6年能登半島の復興へ(オフグリッド)
13(C-6).能登半島の復興へ(地域留学)
1(A-1).断層型巨大地震である能登半島地震の特長
冒頭で能登半島地震は巨大な断層型地震であると触れましたが、大規模な隆起が広範囲で発生したことも特徴であります。隆起は志賀町から珠洲市にかけてのおよそ80キロの範囲で確認されており、最大は輪島市門前町吉浦で5.5mとの報告もあります。日本列島や日本海の形成に関係していそうです。
【参考サイト】
災害列島特集記事 NHK
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 情報地質研究グループ 尾崎 正紀、井上 卓彦
この情報は2019年と能登半島で2022年から発生した一連の群発地震よりも前に発表されたものですが,防災上の重要性に触れつつ、ユーラシア大陸と日本列島を分離させた約3,000万年にわたる日本海の形成史が記録についても説明されています。
能登半島地震と日本海側地域の断層──地形・地質・構造調査から分かること
東京大学 UTokyo FOCUS
(石山 達也 地震研究所日本列島モニタリング研究センター准教授)
能登半島地震の発生メカニズムや断層の活動状況を解明するため、詳細な調査が実施されました。発見できた事として、地震の震源域と断層の関係性、地震による地形変化の具体例、質構造の特性とその影響になります。
日本海がどうしてできたか知っていますか? 2000万年前に起きた大イベント
海洋研究開発機構
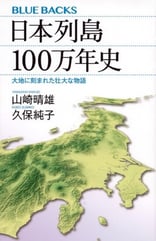
日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語
山崎晴雄、久保純子(ブルーバックス)
日本列島の特長的な地形の成り立ちが詳しく書かれています。この中に「日本海の開裂と日本列島の誕生」について1項目4ページでかかれていますし、その他の地域のことも書かれています。
[出版社のサイトへ]
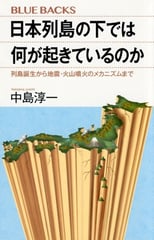
日本列島の下では何が起きているのか 列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで
中島淳一(ブルーバックス)
日本海が拡大しているとき、日本列島には非常に大きな変化が起こっていました。場所は異なりますが能登半島地震時にも関係していたといわれる、内陸地震の発生と水の関係についても触れられています。
[出版社のサイトへ]
★関連学問:「固体地球科学」のページへ
2(A-2).豪雨の中でも恐ろしい線状降水帯
線状降水帯とは、次々と発生する発達した積乱雲によって、2~3時間にわたってほぼ同じ場所を通過していき、強い降水をともなう雨域です。それは線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度とされています。予測が難しく、またこれまでの大雨対策では対応できないなど課題が多いです。能登半島でも地震から10カ月を迎えようとしていた令和6年9月下旬に発生しました。
【参考サイト】
地震襲った能登地方に記録的豪雨、沖合の高い海面水温が極端雨量の要因に 「複合災害」へ備えを
内城喜貴:科学ジャーナリスト、共同通信客員論説委員
サイエンスポータル
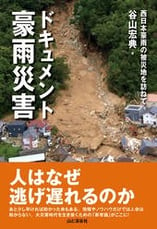
ドキュメント豪雨災害 西日本豪雨の被災地をたずねて
谷山宏典(山と溪谷社)
平成30年(2018年)の西日本豪雨のときにも線状降水帯が発生しました。各地に襲った豪雨に人々がどのように反応したのか、詳細に記録されており災害現場の実態がよくわかります。
[出版社のサイトへ]
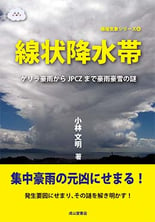
線状降水帯 ゲリラ豪雨からJPCZまで豪雨豪雪の謎
小林文明(成山堂書店)
線状降水帯や日本海の冬季の強い風など極端な雨、風の現象について詳しく書かれており、さらにそれらからの防災対策についても触れています。気象学に興味のある方、治体・団体の防災担当者の方、大雨の被害の多い地域にお住いの方におすすめとしています。
[出版社のサイトへ]
★関連学問:「気象・海洋物理・陸水学」のページへ