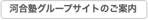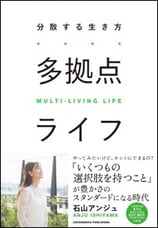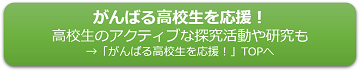防災・復興と地域活性化を研究・探究してみよう!
能登の未来を考えることは、すべての地方の未来を考えること。その参考やヒントになる本を、最前線の防災工学者が贈る 〈3〉
信岡尚道先生 金沢大学 能登里山里海未来創造センター
8(C-1).令和6年能登半島地震からの社会インフラの 復旧
【参考サイト】
石川県ホームページ
国土交通白書 令和6年版
令和6年版 国土交通白書2024(国土交通省)
令和6年に発生した能登半島地震の災害状況をまとめたあと、1月1日の発生からの対応やインフラの応急復旧、本格復旧への道のりについても記されています。2週間で行われた能登半島へのアクセス道路の緊急復旧の説明では、緊迫感あふれる活動が伝わってきます。また、国土交通省による物流・物資支援や生活・生業支援についても書かれています。
国土交通省 能登復興事務所チャンネル(YouTube)
★関連学問:「土木計画学・交通工学」のページへ
9(C-2).令和6年能登半島の復興へ(能登の魅力)
復興とは全く新しいことを考えるよりも、その地域の良い点を伸ばす、これまでの挑戦を成功まで引き上げる観点が重要です。
次に紹介する能登半島について震災より5年前に書かれた本ですが、能登半島のまちの歴史、まちの良い点と課題がまとめられています。冒頭で紹介した石川県の創造的復興プランと比べながら読んでみましょう。
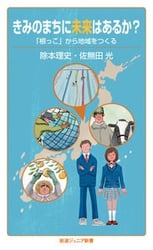
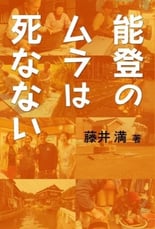
能登のムラは死なない
藤井満(農山漁村文化協会)
ここでのムラ=集落と読みかえてもよいだろう。著者は新聞記者として2011年~2015年まで能登を取材して文化や生業に熟知し、また震災後の奥能登の地をめぐって被災状況を直接確認した上で、奥能登の4市町の集落の能力を明記し、復興への希望を示している本です。
[出版社のサイトへ]
【参考サイト】
インフルエンサーひろゆきさんが語る能登の未来の可能性の動画を紹介します。
【ひろゆきin被災地】旅で感じた能登のリアル、旅で見えた能登の未来【まったり雑談with友人ひげおやじ】(YouTube)
★関連学問:「都市計画・建築計画」のページへ
10(C-3).能登半島の復興へ(中越地震からの復興を学ぶ)
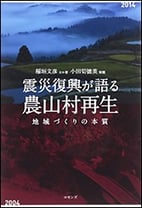
震災復興が語る農山村再生 地域づくりの本質
稲垣文彦(コモンズ)
中越地震は過疎高齢化が進んでいた旧山古志村を襲いました。そこは農山村地域でした。地震からの復旧・復興に加えて地域づくりまでを実践した記録が記されています。
過疎高齢化地域の災害からの復興のお手本となるものであり、能登半島の復興にも活用することが期待されます。
[出版社のサイトへ]
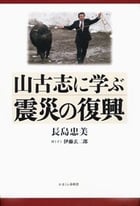
山古志に学ぶ震災の復興
長島忠美 聞き書き:伊藤玄二郎(かまくら春秋社)
山古志の復興の先頭にたった元村長で後に国会議員も務めた長島忠美(故)の話を書き下ろした本です。復興におけるリーダーとは、それが読み取れる本です。
[出版社のサイトへ]
11(C-4).能登半島の復興へ(関係人口・二拠点居住)
人口減少が進む地方では、人口増の策として移住と観光を挙げることがありますが、それには限りがあります。移住でもない形として、関係人口と二拠点(多拠点)居住が注目され始めています。能登半島の創造的復興プランの中でも、リーディングプロジェクトの取組1として「復興プロセスを活かした関係人口の拡大」をうたっています。

都市と地方をかきまぜる 「食べる通信」の奇跡
高橋博之(光文社新書)
著者は関係人口の第一人者。東日本大震災当時に岩手県議員であった著者は都会から被災地への支援者と交流し、都会の人が地方に求めるものを認識します。それは災害時でなく平時でもなりたつものだと。定住ではハードルが高いが、しばしば都会から地方に訪れることは可能と、関係人口を提唱しています。
[出版社のサイトへ]
※続編が、2025/3/18に発売されます。
関係人口 都市と地方を同時並行で生きる
高橋博之(光文社新書)
著者は石川県令和6年能登半島地震復旧・復興アドバイザリーボード委員を務めています。能登半島の復旧・復興への支援の実践経験を踏まえ、この本の中で能登半島における関係人口について述べています。
★関連学問:「観光学」のページへ
12(C-5).能登半島の復興へ(オフグリッド)
オフグリッド(Off the grid オフ・ザ・グリッド)とは、電力、ガス、水道など生活に必要なライフラインなどを、公共の大規模な施設に依存せず、独立して確保できるようにするものです。能登半島地震では広範囲で大きな揺れにより、遠くから送られてくる電気、水道が使用できなくなり、復旧にも大きな時間がかかりました。この課題を解決する一つの方法として、オフグリッドがあります。
【参考サイト】
<検証>2024年能登震災 第7回 令和6年能登半島地震から考える農村地域のインフラ自治の可能性
神﨑 淳子 金沢星稜大学経済学部経営学科准教授
自治体問題研究所
集落存続への再生可能エネルギー(NHK地域づくりアーカイブス)

小さいエネルギーで暮らすコツ
農文協:編(農山漁村文化協会)
太陽光で電気や温水、水の力で小推力発電などを、実際に活用されている現場の写真や説明もふんだんに取り入れ、自ら、集落でエネルギーを得ていく方法が記されています。オフグリッドとしてだけでなく、エネルギーはどのように作ることができるのかを学ぶにも、よい本です。さらに食べ物つくりに活用するなどの応用も書かれています。
[出版社のサイトへ]
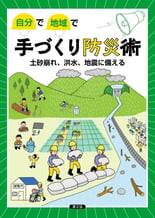
自分で地域で 手づくり防災術 土砂崩れ、洪水、地震に備える
農文協:編(農山漁村文化協会)
災害時にお金などに頼らず、電気、トイレ、風呂、食べ物を自ら作り出し確保する方法が紹介されています。また行政に頼らない、土砂災害対策、豪雨災害対策なども紹介しています。
[出版社のサイトへ]
★関連学問:「地球資源工学・エネルギー学」のページへ
13(C-6).能登半島の復興へ(地域留学)
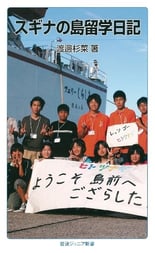

★関連学問:「教育学」のページへ
番外:被災地につなげる災害ボランティア
前向きに被災地を支援、とくに地方の被災地を積極的に多くの人が関わり支援していくことは重要です。支援といっても様々なものがあります。災害ボランティアに関係する情報を紹介します。
【参考サイト】
日本財団災害ボランティアセンター(YouTube)
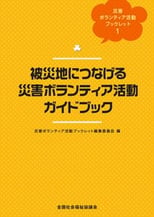
被災地につなげる災害ボランティア活動ガイドブック
合田茂広、上島安裕、災害ボランティア活動ブックレット編集委員会:編(全国社会福祉協議会)
被災地の災害ボランティアは、高齢化が進んでいる地域ほど重要な存在となっています。初めて参加する方などの不安を除いてくれる本です。わかりやすく書かれており、まずはChapter2の「準備する」ができていれば参加OKです。
[出版社のサイトへ]
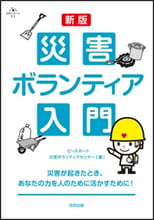
新版 災害ボランティア入門
ピースボート災害ボランティアセンター:編集(合同出版)
災害ボランティに関心をもったときに、まず読むのに良い本。災害現場の状況で知っておくべき基本事項、ボランティアとして活動するために必要な心構えや持参するものなどが書かれています。
[出版社のサイトへ]
★関連学問:「社会学」のページへ
信岡先生のプロフィール
信岡尚道 金沢大学 能登里山里海未来創造センター(2025年4月より)。元茨城大学教授 防災工学。令和6年能登半島地震の津波による海水の遡上高7.5mを新潟県上越市で計測する。この高さだけで言えば能登半島地震津波で最高クラスの高さ、さらにそれは津波と波浪の重なりによる遡上高と物理的考察を行うなど、見た目よりも事実、真実に迫まることを心がけた研究をしている。現在は、あるべき高齢化過疎地域の大震災からの復興を、研究者としての最後の大きな研究テーマに設定の上、活動している。最近は、大切な妹さんを石巻の大川小学校の被災で喪った、1996年生まれの若手の映画監督である佐藤そのみさんに出会い、映画『春をかさねて』の製作や広報を応援している。
金沢大学 能登里山里海未来創造センター