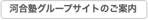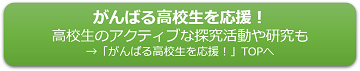<本を通した学問への出会い方入門編>
本のページの向こう側へ 隠された扉を開けるための読書
渡邊十絲子さん 詩人・書評家
「大学で学ぶ」と言うと、「確立された学問分野」があり、そこに仲間入りをしていくイメージがある。しかし学問分野はひとつひとつ独立しているわけではなくて、互いに関連しながら世界全体をカバーするものだ。ある学部学科で学びながら、自分の興味関心の方向へ突っ走っていって、無我夢中で研究して、そこから新しい学問分野が開けることだってありうる。
教卓からこちらを向いて授業をするような本ではなく、著者が自分の興味関心へとつき進んでいる後ろ姿を見せる本を読んでほしい。そういうものこそが、高校生の心に響く書物だ。これまでに「みらいぶっく」で紹介された本も含めて、そんな本をここに集めてみた。
一冊の本にはたくさんの隠し扉が用意されていて、寄り道も脱線も自由だ。物理学の本を読んでいて文体の精妙さに目をうばわれ、自分の中で「名文とはなにか」がテーマになってもいい。方言の現地調査の本を読みながら鉄道整備の歴史が気になってもいい。海外の科学書が読みにくくて翻訳の問題を発見することだってある。
その本の主旨を読み取ることが読書の目的だと考えてはいけない。それは効率主義の考え方であって、「こうすればこうなる」というマニュアルに支配された世界を生きることにつながる。そこに発展性はない。世界はつねに「新しいものの見方」「独創的な考え方」によって書き換えられていかないと、自然に衰退してしまうものなのだ。だから、与えられた知識をお行儀よく身につけることを、読書のときには忘れていい。好きなように読んでいいし、終わりまで読み通さなければならないということもない。
以下にあげるのは、読み手しだいでいくらでも「隠し扉」が発見できるような名著だ。自分にとっておもしろい箇所、興味をひかれる記述、そういうものにひたすら目をうばわれていればそれでいい。おもしろい点がなければ、それはあなたにとってその本との出会いのタイミングが「まだ」だっただけである。

『先生、イルカとヤギは親戚なのですか!』
小林朋道(築地書館、2025)
小林朋道の「先生!」シリーズは、「自分は理系じゃないから」などと言わずにどれか一冊手にとっておいて損はない本だ。『先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!』(築地書館、2007)から『先生、イルカとヤギは親戚なのですか!』(築地書館、2025)まで、年に一冊ずつ出ている。鳥取環境大学小林ゼミの活動記録である。
「ヤギ部の新入部員」が人間ではなくてヤギである事実を知るのもおもしろいが、動物行動学という、フィールドワークや実験によって成り立つ研究をしている人たちが、どう日常を過ごし、どんな事件に巻き込まれているのかがわかる。「研究室」をイメージしたい人にも向いている。著者はなるべくおもしろおかしく書こうとしているから、日常にひそむ笑いのポイントを研究したい人にも向いている。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「動物生理・行動」のページへ

『人類と建築の歴史』
藤森照信(ちくまプリマー新書、2005)
マンモスのいた時代にさかのぼって「建築とは何か」を考える本。洞窟の中で壁画を描いた人は何を感じ、どんなことを考えていたか。その時代から「この洞窟は他の洞窟より住みやすい」という判断があったはずだ。その「住みやすさ」とは何なのか、という話から、古今東西の建築へと話は広がる。
この本から、たとえば「宗教建築は人間の意識をある方向に誘導するように作られている」ことに興味を向けてもいい。そこから宗教図像学のほうへ行ってもいいし、神社仏閣と教会建築の違いに注目する人もいるだろう。それとはまったく違う方向から、海外の建築思想を日本がどう受け入れてきたかを調べてもいい。たくさんの扉を開くことができる。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「建築史・意匠」のページへ
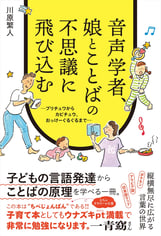
『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』
川原繁人(朝日出版社、2022)
言語学のなかでも音声学を専門とする著者が、自分自身の子育てを通じて幼児の発音を研究している。ラ行がヤ行になる幼児発音(「いらない」が「いやない」になるなど)や、幼児らしい言い間違いにも法則がある。
ここから文法という法則のしくみに興味を持ち、国語学や比較文法のほうへ分け入っていく人もいるだろうし、「自身の子を題材にした研究」がおもしろいと思ったら、麻生武『6歳と3歳のおまけシール騒動 贈与と交換の子ども経済学』(新曜社、2023)などの名著がたくさんある。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「言語学」のページへ

『翻訳ってなんだろう』
鴻巣友季子(ちくまプリマー新書、2018)
本書は、古典的名作(英語)を新しく翻訳しなおしている著者の翻訳教室。英語と日本語は、当然のことだが、一単語ずつの対応関係にはない。異なる言語でものを考えるということは、違う枠組みやものさしで世界を見るということだ。翻訳者の書いた随筆には名作が多いから、探していろいろ読んでみて、文学の世界を覗いてもいい。ことばのしくみそのものに興味がわいたら言語学の広い広いフィールドを探索しに行けばいい。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「英米・英語圏文学」のページへ

『「思春期を考える」ことについて』
中井久夫(ちくま学芸文庫、2011)
本書は、高校生にとってやさしい文章ではない。でも、読書を好む人ならこの著者の本にいつかはたどりつくと思う。精神科医としての臨床経験から、人間の心についての深い洞察が生まれている。ここから人間の心に興味を持ったら心理学や精神医学の本に進めばいいし、自分の思春期にひきつけて読んでもさまざまな発見があり、自分を知るきっかけにもなるだろう。この文庫自体は現在新刊書店では入手できないが、この著者の文章は『中井久夫集』(みすず書房、2017~2019)で読める。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「教育心理学」のページへ
以下に挙げるのも、読めばさまざまな角度からの発見がある本。あくまでも「自分にとって」おもしろいポイントを探すつもりで読んでみてほしい。
「神が仕組んだとしか思えない」美しさに出会う──カタツムリの「巻き」の向きから宇宙の法則まで

『進化のからくり』
千葉聡(講談社ブルーバックス、2020)
生物学のなかでも進化論関連の本はたくさんあるが、この本を第一におすすめする。文章がすばらしい。著者は陸貝(カタツムリなど)の研究を通じて、ダーウィンの進化論の「その後」を切り開いている。著者が参加した「小笠原諸島 南硫黄島自然環境調査」はテレビ番組(NHKスペシャル「東京ロストワールド」(1)「南硫黄島」)にもなり繰り返し放送されているから、見た人も多いだろう。
研究が社会の役に立つものであるよう強いられる現実や、教授の研究に院生を参加させ「下働き」をさせることの是非なども語っている。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「生物多様性・分類」のページへ
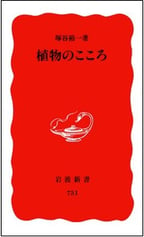
『植物のこころ』
塚谷裕一(岩波新書、2001)
生物学は動物を研究するものばかりではない。植物は一見して「脳がない」「感情もことばもない」、だから下等なものだと思われがちだが、それは誤解だ。生き物の魅力はモフモフやモチモチだけではない。この本は精妙なシステムを切り回し、特殊能力を発揮して生きる植物の世界を案内してくれる。親しみやすさと格調高さの両立した名文も味わいたい。
[出版社のサイトへ]

『宇宙は数式でできている』
須藤靖(朝日新書、2022)
物理学者は宇宙の法則を「発見」するのか、「発明」するのか。宇宙の観測を通じて、人間が予想していた理論の正しさが証明されるとき、宇宙物理学者はその法則に「神が仕組んだとしか思えない」美しさを見いだす。この著者も名文家である。この本は違うが、お笑いモードの文章も絶品である。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理」のページへ
「社会」の細部に分け入る──まちを記録し、人の話を聞く

『考現学入門』
今和次郎(ちくま文庫、1987)
1923年の関東大震災後、バラック(仮住まいのための小屋)が立ち並ぶ東京で、著者は「考現学」を始めた。道行く人の服装や学生の持ち物などありふれたものをスケッチし、記録として残す。生活や流行は低俗なもので学問の対象ではないと見られていたが、それを新たな研究対象としたのだ。一般に価値がないと思われているものは記録に残りにくいが、それらに目を向けるのも立派な「学問の態度」である。
[出版社のサイトへ]

『調査する人生』
岸政彦(岩波書店・2024)
著者は社会学者。人の話をひたすらに聞き、記録する。エスノグラフィー(民族誌)の手法である。この本では、同じように「人の話を聞く」ことに人生の時間を捧げている研究者たちと対談をしている。対談の相手は、女性ホームレスの話を聞いている人、在日コリアンの移動の歴史を書き残そうとしている人、などなど。もちろん話し言葉であるし、話題が具体的だから読みやすい。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「社会学」のページへ
ことばの世界を探検する──「成り立ち」と「現在使われていることば」とのつながりを知る
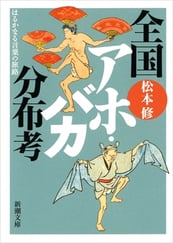
『全国アホ・バカ分布考』
松本修(新潮文庫、1996)
もとはテレビ番組「探偵! ナイトスクープ」に寄せられた「アホと言う地域とバカと言う地域の境界はどこか」という質問だった。しかし「タワケ」ゾーンや「ダラ」ゾーンなどの発見を経て、調査は壮大なものになる。全国への出張取材、古い文献の調査。ついに「方言地図」を完成させるまでのノンフィクションだ。ジャンルとしては、言語学(方言)と社会調査にまたがる。
[出版社のサイトへ]

『漢字と日本人』
高島俊男(文春新書、2001)
漢字とは「中国から輸入した表意文字」だと、たいていの日本人は思っている。しかしその認識は解像度が低すぎる。漢字は「一文字が一単語」であり、「活用がない(一単語のかたちが変化しない)」。だからそれを、活用がある(行か・ない、行き・ます、行く…などと変化する)日本語にあてはめると無理が出る。中国語と日本語は発音体系もかなり違うから、「音読み」にも問題が生じる。こうした問題について、中国文学の研究者がチャキチャキの語り口で解説してくれる本。目からウロコの爽快感。言語学、日本語学への入り口だ。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「日本語学」のページへ

『はじめての言語学』
黒田龍之助(講談社現代新書、2004)
言語学に興味をもったらまずここから始めるといい。言語学案内の本である。言語学のフィールドはとてつもなく広く、あなたが興味を持つものがどこにあるのかを探しあてないと、迷子になる。著者は語学の先生だがエッセイの名手でもあるから、学問はいったん横に置いて、純粋な楽しみのための読書として著書をかたっぱしから読むのもアリ。
[出版社のサイトへ]
美のありかをさぐる──美はどこに存在するか、人は何を「美」だと思うか
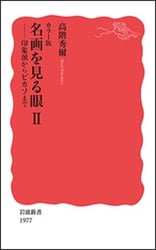
『カラー版 名画を見る眼』
高階秀爾Ⅰ・Ⅱ(岩波新書、2023)
もとは1969年に発行された、岩波新書の定番中の定番。世界の名画を見ながら、「絵を語るとはどういうことか」を知ることができる。絵を見て感じたことを言語化するのは習練を必要とする技術であって、なんの準備もなく「すなおに」書いても歯が立たない。もっと言えば、言語化することで初めて自分の考えや感じ方が作られていくのだ。ジャンルは美術批評、美学。
[出版社のサイトへ]

『カラー版 絵の教室』
安野光雅(中公新書、2005)
絵の専門家ではない人が趣味で絵を描きたいと思ったときに、突き当たる壁がいろいろある。画家がその「壁」について語った本だ。自画像を描くとき、何を着たらいいか、表情はどうすべきか。遠近法にはどこまで忠実であるべきか。それらは技術の問題ではなくて、「絵とは何か」につながる哲学的な問題であり、シンプルな正解などない。これほど誠実な「教室」は見たことがない。芸術分野にかぎらず、教育を志す人は読んでみてほしい。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「美学・芸術諸学」のページへ
「自分」と「他者」を知る──あなたと他人とはどこが違い、何が共通点なのか
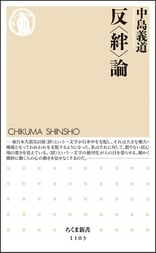
『反〈絆〉論』
中島義道(ちくま新書、2014)
東日本大震災のあと、マスコミが「絆」の大合唱に染まった時期がある。なんでもかんでも「絆の大切さ」で片づけられて、空疎なことばになってしまった。「絆」という、反論や否定をしにくい善のイメージは、人を思考停止に追い込み、ときに暴力にもなりうる。哲学はこうした問題をどう扱うのか。みんな一度は哲学に触れてみてほしい。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「哲学・倫理学」のページへ

『日本人の〈原罪〉』
北山修、橋本雅之(講談社現代新書、2009)
日本は諸外国と比較して自殺率が異常に高い国だが、それはなぜか。日本人の心の根底にある感受性を解き明かし、それが人の生き方や価値観、社会構造にどう表れているかを語る。どの国においても、感受性の底の部分を作っているのは神話や昔話であるが、この本も日本の昔話を題材にしている。精神医学と国文学(神話)を専門とする二人の共著である。
[出版社のサイトへ]
☆関連学問:「日本文学」のページへ

『目の見えない人は世界をどう見ているのか』
伊藤亜紗(光文社新書、2015)
人間は外界から情報を得るために「五感」を使うが、その中でも視覚への依存度は飛び抜けて高い。またそれだけに、目が見えないことは重い障害とされる。しかし目が見えない人は視覚に頼らない外界探索ができる。「見えない」というマイナス点を持っているが、「見える人にはできないことができる」というプラス点も持っているのだ。そもそも「見る」とはどういうことなのか。視覚に頼らない人が描く世界像はどういうものなのか。これは身体論の本だが、著者のもともとの専門は美学や現代アート。人間の身体の可能性を実感しよう。
[出版社のサイトへ]
実際の研究を覗いてみる──論文はどうやって書くのか

『研究を深める5つの問い』
宮野公樹(講談社ブルーバックス、2015)
この本はジャンルを超えたものとして紹介しておきたい。研究をしたい、論文を書きたいと思っても、行く手にはなかなか手ごわいハードルが多数存在するのが現実だ。それらにどう立ち向かうか。研究者の思考方法とはどんなものか。それをこの本は伝えている。著者は「異分野融合」や大学のありかた、研究に関する政策などが専門分野である。
[出版社のサイトへ]
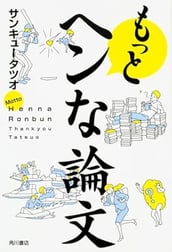
『ヘンな論文』
サンキュータツオ KADOKAWA/角川文庫 2017
『もっとヘンな論文』
サンキュータツオ KADOKAWA/角川文庫 2020
著者はお笑い芸人であると同時に大学講師でもある。この本は、ちょっと変わった論文を数多く紹介している。「女子校生と〈男子の目〉」「古今東西の湯たんぽ」などなど。ものによっては驚くほどユルいテーマだったりもするが、しかし紀要(大学や研究機関が定期的に発行する論文集)に掲載されている、れっきとした論文だ。論文の世界を覗き見てみたい人におすすめする。笑って読める。
[出版社のサイトへ]

渡邊十絲子(わたなべとしこ) プロフィール
詩人・書評家
1964年東京生まれ。早大第一文学部文芸学科卒。卒業制作の詩集で小野梓記念芸術賞受賞。その後、詩集『Fの残響』(河出書房新社)、詩作の入門書『ことばを深呼吸』(東京書籍)など、詩にかかわる書籍を出版。雑誌『本の雑誌』で書評コラム「馬の耳に新書」を13年間連載し、本当に面白い本、読むべき本を提案。現在、「毎日新聞」「週刊新潮」など各紙誌で書評を執筆中。
『今を生きるための現代詩』(講談社現代新書)では、「いまの自分が気づくことのできない美しい法則が、世界のどこかにかくされてあることを意識するようになる。詩に役割があるとしたら、それだけでいいのだと思う」と語り、国語教育や大学入試でも注目。