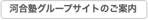高校図書館を使ってみよう ~高校の図書館司書・先生からのメッセージ <1>

図書館は気持ちがリラックスできる場所
長崎南山高校 学校司書 松浦純子先生
★おススメ本は、『アルコールで走る車が地球を救う』
【図書館への誘い】
図書館は皆さんが思っている以上に気持ちがリラックスできる場所です。使わないと損な場所です。皆さんにとって図書館が持続可能ないい場所へと続いていくようにそれぞれが努力しましょう。
【探究活動にも図書館を使って】
電子図書館を含めて図書館には多くの資料・情報が収集されています。ぜひそれを活用するスキルを身につけてほしいと思います。本校でも探究活動に図書館が使われることが多いです。インターネットで情報を集めることは簡単ですが、最後は図書館資料を求めてやってきます。
→おススメの「環境問題・エネルギー問題について考える本」 詳しくはこちら

本当に出会うべきものは、自分で手を伸ばさないと得られない
山崎学園富士見中学校高等学校(東京都) 司書教諭 宗愛子先生
★おすすめ本は、『AIにはない「思考力」の身につけ方 ことばの学びはなぜ大切なのか?』
【図書館への誘い】
学校図書館の良いところは、具体的な「何か」読みたい、知りたい、調べたいという理由がなくても、ふらりと立ち寄ることができて、気になった資料(本や雑誌、新聞)を自由に手に取ることができることです。本を借りたい友人につきそって来た生徒が、たまたまそこに展示してあった本を借りてみたら面白かった、放課後友達との待ち合わせに図書館に来て、書架を眺めていたら気になる本があって読み始めたら止まらなくなった……、こういったエピソードが、学校図書館にはたくさんあります。
ポイントは、偶然出会うにしても学校図書館に行かないと決して出会えない、ということです。今は大量の情報が身近なスマホで入手できるので、図書館に行かなくても情報は得られると思うでしょう。でも、あなたが本当に出会うべき「何か」は、自分で選んで手を伸ばさないと入手できないものです。学校図書館の利用者は、生徒の皆さんです。玉石混淆のネットとは違い、生徒のために厳選された資料があるのが特徴です。時間を作って、学校図書館に足を運んでみましょう。学校司書はいつでもあなたの来館を待っています。
→→おススメの「思考力を高めたり、学び方について知れる本」はこちら

一生かかっても読めない冊数の本に囲まれて
六甲学院高校(兵庫県) 図書館司書 澄川久美先生
★おススメ本は、『火星の人』
【図書館への誘い】
とりあえず、気になった本や雑誌は、手に取ってパラパラしてみてください。何か気になるテーマや話題があるのなら、新書をおすすめしたい。それらは全部読まなくていいし、飛ばしながら読んでもよい。つまらなかったら違う本に変えればいいのです。
図書館は入ってくる人を拒みません。一生かかっても読めない冊数の本に囲まれて、座って外を眺めてボンヤリしていてもいいのです。
→「知る・考える・やってみる・わかる!?」おススメ本 詳しくはこちら

図書館で、本屋やネット書店ではできない体験を
千葉県立東葛飾高校 公民科(「公共」) 内久根直樹先生
★おススメ本は、『「みんな違ってみんないい」のか? ――相対主義と普遍主義の問題』
【図書館への誘い】
図書館の使い方に正解はありません。
友達や親戚の家にお邪魔したとき、本棚をちらっと覗くと、その人がどんな本を読んでいるのかが分かり、人柄を想像できることがあります。それと同じように、図書館にどんな本が新しく入荷されているのか、どんな特設コーナーが設けられているのかを定期的にチェックしてみるのはどうでしょうか。
また、「3冊借りる」というルールを決め、分類番号の若い順に一巡してみるのも面白いかもしれません。本屋やネット書店では味わえない、新しい発見があるでしょう。他にも、学校によっては図書館を活用したワークショップが開催されることがあります。興味がなくても、気軽な気持ちで参加してみるのもよいでしょう。
【「探究」に図書館を活用するなら】
「総合的な探究の時間」では、同じ関心を持つ生徒同士や友人と協力し、著者を招く「オーサービジット」などを図書館で企画してみてはいかがでしょうか。大学や研究機関など、さまざまな分野の専門家の先生方は、自分の専門分野に高校生が関心を持ってくれることを嬉しく思うはずです。身近な先生に協力をお願いするのもよいでしょう。
例えば、招いた先生と直接交流することで、大学での学びを具体的にイメージできたり、「総合的な探究の時間」のレポート発表の質が向上したりすることが期待できます。

ただ司書とおしゃべりするために来てもいいよ
鎮西学院高校(長崎県) 司書 今村節子先生
★おススメ本は、『あなたを丸めこむ「ずるい言葉」』
【図書館への誘い】
何か目的がなくても来ていいのが図書館だと思います。「本を読まなきゃ」と思わなくてもよいので、ふらりと図書館を訪れてほしい。ぼーっとしに来てもいいし、書架の間を巡って本をぼんやり眺めてもいいし、ただ司書とおしゃべりするために来てもいいよと伝えたいんですよ。
おしゃべりをするようになってからいろいろと本に関する相談(受験対策や興味のある分野についてなど)をしてくれるようになる人も多いし、図書館を“居場所”にしている人もいます。
まずは図書館という場と司書に馴染んでみてください。そのうち本が単なる“字が詰まった紙の集合体”から意味を持つ存在に感じてもらえたら嬉しいな。元々の本好きの人にはさらに読書力を広げたり高めたりするお手伝いもしますよ。
→おススメの「なんだかためいきばかり出てしまったら読む本」 詳しくはこちら

就職や進路で悩んでいるなら、まずは本を読んでみて
長崎市立長崎商業高校 粟田純子先生
★おススメ本は、『銀の匙』
【図書館をこう使おう】
将来に向けてはっきりとした考えがなかったり、いろんなジャンルへの就職、進学を悩んでいるのでしたら、まず興味を持っていろいろな本を読んでもらうことが一番と思います。
また、小論文に使えるようにと、新書で観光、地方再生、地元企業、マーケティング、スポーツ、介護、医療、看護の周辺で新しい本、理論ではなく具体的に書かれたものを積極的に入れるようにしています。
→おススメの「進路や将来に悩んでいるときに読む本」 詳しくはこちら

遠慮なく司書さんを頼ってください
千葉県立柏高等学校 学校司書 油納朝子先生
★おススメは、『旅に出よう : 世界にはいろんな生き方があふれている』
【「探究」に図書館や本を活用するなら】
「探究」するテーマが決まらなくて困っている人は、図書館の中をぶらぶらしてみましょう。背表紙のタイトルをなんとなく見ているうちに、興味が惹かれるテーマがあるかもしれません。新聞もお勧めです。図書館には必ず新聞があります。「探究」のテーマは身近な事柄でももちろん良いと思いますが、新聞には地球規模でいろいろな情報が載っているので、そこからちょっと深掘りしてみたいなと思えるものがあれば、それをテーマにするのも良いと思います。自分が生まれた日の新聞を見てみてもおもしろいかもしれません。
テーマが決まったら、インターネットの情報だけでなく、必ず関連する本でも調べてみましょう。関連する本も、1冊全部読む必要はありません。どんな本を読めば良いかわからない、本が探せないという場合は、司書さんに気軽に質問しましょう。司書さんは、調べ物をする人の手伝いをするのが仕事ですから、学校図書館でも、市町村の図書館でも、遠慮なく司書さんに頼りましょう。
→おすすめ本「進路や将来に悩んでいるときに読む本」 詳しくはこちら