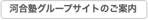高校図書館を使ってみよう ~高校の図書館司書・先生からのメッセージ <2>

司書は資料提供のプロ。きっと突破口になる
渋谷教育学園渋谷高等学校(東京都)司書教諭 前田由紀先生
★おススメ本は、『華氏451度』
【探究に図書館を使うなら】
高校3年生になると、「もっと本を読んでおけば良かった」という生徒がいます。受験に対して、基礎体力となる思考力、語彙力、論理力等が必要となってくるからだと推測します。
本校では、1万字の卒業論文を書くことが課せられますので、テーマ決めや関連資料の問い合わせが多いです。なかなか関連資料がないという場合も、キーワードを少し変えてみたりすると増えたりします。先行研究の論文検索には、CiNiiを、図書検索には、カーリルを、時事テーマであれば、新聞検索を勧めています。
資料相談をレファレンスと言いますが、司書はこの資料提供のプロなので、問い合わせてくれると非常にうれしいです。何とか利用者の手助けになるよう努めているので、是非どこの図書館でも司書に気軽に声を掛けてほしいと願っています。きっと突破口になります。また、外部コンクールも多種多様にあるので、挑戦してみるのも良い動機づけとなるでしょう。
→おススメの「言論の自由、プロパガンダ、政治について考える古典」 詳しくはこちら

社会にとって有益な提案となるために
中央大学杉並高等学校(東京都) 国語科 小泉尚子先生
★おすすめ本は、『職業は武装解除』
【「探究」に図書館や本を活用するなら】
探究で「やってみたい」と思うことについて、先行研究があるか知る手がかりを確実に得られるのが図書館です。たとえば、「睡眠時間と学習効率の相関性を知りたい」「地域の歴史について詳しく調べてみたい」と思ったとき、これまでにどんなことが明らかになっているのか、どのような研究方法がとられているのか等、図書館でまず資料(史料)を探すことが必要です。
自分で考察したことが社会にとって有益な提案となるためには、先行研究を踏まえていないとできません。アイディアを磨いていくために図書館を活用してください。

なんとなく、直感で!その積み重ねがあなたをつくる
座間総合高等学校(神奈川県) 国語 宮下翔吾先生
★おすすめ本は、『ブルーピリオド』
【図書館への誘い】
自分が高校生の頃、「図書室へ行く」という行為は高尚なことのように感じていました。何かしらの大義名分をもっていないと、その部屋の扉を押してはいけないような気がしていました。そんなことないよ、気楽においでよ、もっとラフに、適当にでいいんだよと伝えたい。
自分自身の興味関心に基づいて、特定の分野の目的の本をスッと手に取ることも大切ですが、直感で、「この本のタイトルと体裁が良いから!」という理由で、まずは手に取ってもらえたらなと思います。ぱらぱらとめくって微妙だったら、棚に戻せばいい。いわゆる、そんなジャケ買いの本が、読み進めていくうちに、自分の心にピタッとはまったりもします。
「なんとなく、直感で」。その積み重ねが、あなたの興味関心となるのです。

自分の考えが変わる瞬間をもたらしてくれる
神奈川県立鶴嶺高等学校 国語科教諭 伊藤雅子先生
★おすすめ本は、『アンネの日記』
【読書への誘い】
自分の考えが変わる瞬時に変わることはそんなに多くありません。ほとんどは時間をかけて経験をして悟っていくもので、時代、経験値の多寡、それらを超えて過去の叡智に触れることができる読書は、自分の考えが変わる瞬間を多くもたらしてくれるものだと思います。読書経験の多い人は、豊かな人生を送れるのではないでしょうか。日常的に読書に親しむ習慣があってほしいと思います。

文学には大きな力がある
栄光学園中学高等学校(国語科・非常勤講師)(神奈川県) 石原徳子先生
★おススメ本は、『妄想する頭 思考する手』
【図書館への誘い】
「物語」以外の本もたくさんあることを知ってほしい。一冊全部読まなくても良いことを知ってほしい。そして、「文学」にもやはり大きな力があることを感じてほしいです。

本や図書館は、みなさんの未来を広げる道具です
早稲田大阪高等学校(大阪府)(旧早稲田摂陵高等学校) 米田謙三先生
★おススメ本は、『地域再生の失敗学』
【図書館への誘い】
本や図書館は、知識を広げるだけでなく、考える力や想像力を育てる大切な場所です。高校生のみなさんには、ぜひ積極的に本を手に取ってほしいと思います。
ある生徒は、図書館の本を活用してプレゼンの資料を作成し、大会に出場しました。それまでは「図書館は勉強のためだけの場所」と思っていたそうですが、さまざまな資料を探す楽しさに気づき、「本を使いこなせることが武器になる」と言っていました。
【探究に図書館や本を活用するなら】
高校の探究活動では、自分の興味のあるテーマを深く掘り下げ、考えをまとめていくことがポイントです。「本や図書館をどれだけ使いこなせるか」 は、探究の質を大きく左右することになります。
🔹 テーマ・課題のヒントを見つける
🔹 資料を集め、情報を整理する
🔹 視点・視野を広げる
📌 「ネットで調べればいい」ではもったいない!
本には「ネットでは出てこない深い情報」や「専門家の視点」が詰まっています。ネットと本の両方をうまく活用すると、探究のレベルがぐっと上がります。
📌 「図書館の使い方がうまい人」が探究を制する!
図書館の検索システムを使いこなしたり、司書さんに相談したりすることで、自分では探せなかった貴重な資料が手に入ることがあります。
📌 「本×探究」は未来につながる!
探究活動で読んだ本が、大学での研究や将来の仕事につながることもあります。興味のある分野の本を読むことは、未来の自分への投資にもなります。
→前ページに戻る