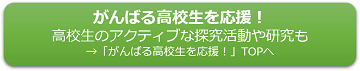高校の図書館司書・先生が推薦!本の魅力 <2>
『華氏451度』ほか
『職業は武装解除』ほか
『ブルーピリオド』ほか
『アンネの日記』ほか
言論の自由、プロパガンダ、政治について考える古典
渋谷教育学園渋谷高等学校(東京都)司書教諭 前田由紀先生

華氏451度
レイ・ブラッドレイ 伊藤典夫:訳(ハヤカワ文庫)
華氏451度とは紙が自然発火する温度であり、この本では焚書を象徴しています。火事を消す消防士をファイアマンと呼びますが、この本では書物を燃やす焚書官を指す近未来のお話です。
登場人物の老教授が、第一に書物の中には、ものの本質があり、第二にそれを消化できるだけの閑暇が必要であり、第三にそこから正しい行動をおこすことだと語るところが心に残ります。その他にも示唆的な問答が巧みで何度読んでも新たな発見がある古典です
[出版社のサイトへ]
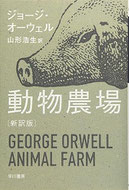
動物農場
ジョージ・オーウェル 山形浩生:訳(ハヤカワepi文庫)
ある農場で、知的なブタが動物たちを団結させ、人間を追い出すことに成功します。理想の動物農場になるはずが、徐々に指導者のブタたちが、 戒律を少しずつ変えて特権階級となっていくところに怖さがあります。他の動物たちがおかしいと気づきながらもそのままに流されてしまっていく過程が見所です。人間の心理を掌握するプロバガンダは、ネット社会となるとより危険性をはらんでいるように思えます。
[出版社のサイトへ]

茶色の朝
フランク・パヴロフ 藤本一勇:訳(大月書店)
「茶色の猫以外は飼ってはいけない」から始まり、次々に茶色以外のものがなくなっていく状況が、主人公と友人のたわいない会話を通して語られ、最後は思わぬ悲劇となっていきます。「茶色党のやつらが最初のペット特別措置法を課してきやがったときから警戒すべきだったんだ」。現在103万円の壁など様々な政策が取りざたされていますが、どのような社会にしていくか、主権者である私たちが政治に関心を持ち続けることの意味を考えさせられます。
[出版社のサイトへ]

前田先生 一問一答
Q1.高校のころに読んで、影響を受けた本は?
司馬遼太郎の『竜馬がゆく』です。歴史上の人物が、初めて生身の人間として感じられ、その時代にタイムスリップしたような感覚がありました。三菱のロゴマークは、土佐藩主と岩崎弥太郎の家紋を、ソフトバンクのロゴマークは、海援隊の旗をモチーフにしています。
Q2.最近読んだ本で、おすすめしたい本は?
湯川秀樹の『旅人』を再読しました。科学者として名を馳せる前の20代までの自伝であるところに親近感を覚えます。若き悩める科学者がいかにして日本初のノーベル賞となる独創的な発想に到達したかの軌跡を辿ることができます。
Q3.感動した映画・印象に残っている映画は?
『Don‘t Look Up !』 地球に危機が迫っているのに、何の手立てもできず、見て見ぬふりの人類の愚かさが克明に描かれています。このような正常性バイアスに人間は陥ることを知っておくことが重要でしょう。
仕事や働くということを考えられる本
中央大学杉並高等学校(東京都) 国語科 小泉尚子先生

職業は武装解除
瀬谷ルミ子(朝日新聞出版)
現在も難民支援や途上国の自立支援に最前線で携わっている瀬谷さんの本です。紛争地で危機的な状況に置かれた人々をただ保護して物理的に環境を整えるだけでなく、その方々の主体性を大事にしながら支援を続けるという姿勢が、学ぶべきところだと考えています。
[出版社のサイトへ]

雪ぐ人 「冤罪弁護士」今村核の挑戦
佐々木健一(新潮文庫)
数々の冤罪を勝ち取った弁護士・今村核さんの仕事ぶりをドキュメンタリー番組に仕立てた佐々木さんによる本です。事実を突き止めるために細やかに調査をする今村さんを知ることで、社会を良くするのは誠実であること、諦めないこと、地道な作業を丁寧に行うことが必要なのだと学ぶのではないでしょうか。
[出版社のサイトへ]
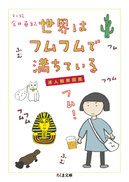
世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑
金井 真紀(ちくま文庫)
海女、石工、インタビュアー、ヴィオラ奏者、牛飼い、占い師、映画の背景画家等、”仕事の達人”がどのようにこなしているのか、どのように仕事と向き合っているのかを記した一冊。皆さんそれぞれの仕事愛が感じられ、ちょっと肩の力も抜け、何よりこんな職業があるんだと知れる楽しい本です。

小泉先生 一問一答
Q1.先生の好きな本のジャンルは?
発達心理学系。おすすめは、成田奈緒子『「発達障害」と間違われる子どもたち』。
一人ひとりと向き合うとき、まずは既成の枠に囚われず、資質を探り当てることが必要だと教えてくれます。
Q2.高校のころに読んで、影響を受けた本は?
遠藤周作『わたしが・棄てた・女』。
最後に主人公が選んだ道は、誰に薦められたわけでもなく選んだ道。むしろ、選ばずに済むようになったのに自ら戻ってきた道。そんな主人公の生き様に触れ、一読すると彼女が自己犠牲の人/優しさに溢れた人/覚悟のある人…というような人間として目に映るかもしれません。けれど、きっと彼女は何も考えず、ただ何かに突き動かされるままにその道を選んだだけなのではないでしょうか。結局、彼女自身が何よりそうしたくてその道を選んだのだ、自分の生き方は自分が選ぶものなのだと思えた本でした。
Q3.最近読んだ本で、おすすめ本は?
鳥羽和久『「学び」がわからなくなったときに読む本』。
「学び」って言葉はどうも胡散臭いな…何をやっても「良い学びとなった」「学びを深められた」、この一言でなんでもまとめてしまえる危うさを感じていたときに出会った一冊です。
日々「学び」に関わる7名の方との対話記録ですが、それぞれのご経験から紡がれる、地に足のついた言葉の数々に触れ、ふわっとした抽象的な概念だった「学び」が確かなものとして形作られていく感覚を味わいました。
本気になることができないと思っている人に
座間総合高等学校(神奈川県) 国語 宮下翔吾先生

ブルーピリオド
山口つばさ(アフタヌーンコミックス)
絵を描くことの楽しさに目覚めた主人公が、東京芸術大学への受験に苦悩したり、東京芸術大学の学生として美術を学んだりする姿を描いた作品。
美大の受験を考えている人、絵を描くことを仕事にしたいと考えている人、美術館の雰囲気が好きな人にオススメしたい。絵を描くことの楽しさ、絵を見るとはどこをどう見るのか、美術大学に関する基礎知識等を学ぶことができます。
[出版社のサイトへ]

左ききのエレン
原作:かっぴー 作画:nifuni(ジャンプコミックス)
大手広告代理店を舞台にした作品です。進路に悩んでいる人、就職したくないと考えている人、本気になることができないと思っている人にオススメしたい。本気で働くのって、何かを創る人って、社会人と呼ばれる人たちの生き様って、かっこいいんだって感じてほしいです。
[出版社のサイトへ]

翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サンダース(創元社)
『世界の路地裏100』のようなノスタルジックな世界観を好む方にオススメしたい。まずは図書室や書店でパラパラとめくってください。西洋を感じさせる洒落た挿絵と、不思議な文字の並びに、目を惹かれるでしょう。
手に入れることができたなら、夕食を終えた後の少し落ち着いた頃に読んでほしい。自分の中にも確かに存在していた、しかし言葉にすることはできなかった、今まで適切な言葉を見つけることができなかった、そんな感情が一つの言葉として、そこにはきっと載っていて、今までに感じたことの共感性に、不思議なカタルシス得ることができます。
[出版社のサイトへ]

宮下先生 一問一答
Q1.先生の好きな本のジャンルは?
文学、芸術
Q2. 高校時代に読んで印象に残っている本は?
森絵都『カラフル』。生前の罪により輪廻のサイクルからはずされた主人公の魂が、天使業界の抽選にあたり、再挑戦のチャンスを得たという設定の物語。作品を通して、少年が成長していくのを感じ、購入した日に、3時間ぶっ通しで読んだ記憶があります。
Q3.最近読んだ本は?
『せんせいあのね 1年1組かしま教室 1.ひみつやで』鹿島和夫
高校1年生までに読んでほしい
神奈川県立鶴嶺高等学校 国語科教諭 伊藤雅子先生

アンネの日記
アンネ・フランク 深町眞理子:訳(文春文庫)
多感な年齢の時期に、戦時下で隠れ家生活をしている少女アンネ・フランクの日記。日常や周囲の出来事をみずみずしい筆致で捉えた彼女のひたむきな心のありようを読むだけで、現代に生きる私たちにも何か訴えかけるものがあると感じられます。特にアンネと同じくらいの年齢である高校1年生までに読むと、より感動すると思います。
「他者に惜しみなく与える」というアンネの考えに感銘を受け、他者への思いやりについて考えさせられました。
[出版社のサイトへ]

塩狩峠
三浦綾子(新潮文庫)
実話をもとにした物語。筆者なりの見解が描かれていて、自分の日常や生き方を考えさせられる話です。高校生のときに読んでおくと、覚悟や高潔な意志ということについて良い方に向かって自分の考えが促されるような気がします。
[出版社のサイトへ]
非真面目(不真面目ではない)で良いのです!
栄光学園中学高等学校(国語科・非常勤講師)(神奈川県) 石原徳子先生

妄想する頭 思考する手
暦本純一(祥伝社)
イノベーションが必要と言われますが、そんなこと言われても…って思いませんか。でも、暦本先生はこうおしゃってます。「真面目なイノベーションが『やるべきことをやる』ものだとしたら、『やりたいことをやる』のが非真面目なイノベーションだ」。そう、「非真面目(不真面目ではない)」で良いのです!
著者は、あなたも使っているスマートフォンの、指で操作する画面(スマートスキン)を発明された、暦本先生。暦本先生が、「妄想」をカタチにする思考の方法を具体的に語った一冊です。教員としては「ルールを絶対視して妄想を潰す日本社会」という章(終章7)に胸が痛みます。
[出版社のサイトへ]

好奇心とクリエイティビティを引き出す伝説の授業採集
倉成英俊(宣伝会議)
「あなたがこれまでに受けた〝伝説の授業″は何ですか?」と「ききまくった」倉成さんの採集授業。
「授業」って、固まった知識を伝達されるだけのものではなくて、自分がどう考えるか、どう感じるか、どう変化するか、揺さぶられるか、…自分が主語になっている時に「伝説」が生まれるものかなと思います。「知識伝達」だとしても、自分が「へえ!」「じゃあ、これは?」と思えるかどうかで、全然違う。
将来「授業」をやる予定の人もその予定がない人も、誰かと関わって、気持ちよく何かを考える時にきっと役に立つ、そして何より楽しい「授業」が満載です。頭がやわらか~くなりますよ!
私は国語科なので、大村はま先生の授業と、もう一つは沖縄でのワークショップがすごく印象的でした。ぜひ読んでみてください。
[出版社のサイトへ]

よくわからないけど、あきらかにすごい人
穂村弘(毎日文庫)
「カメラの詩人」荒木経惟は、「被写体とどう向き合ってるんですか」との問いに「愛しい気持ちをぶつけてくんだよ」「情がなかったら撮れないよ。情に溺れるなって言うけど、本当は溺れちゃえばいいんだよ」という。
歌人でインタビュアーの穂村弘は言う。「(対談相手に)伝えたいことは唯一つ。『目の前に奇蹟のような作品があって、この世のどこかにそれを作った人がいる。その事実があったから、つまり、あなたがいてくれたから、私は世界に絶望しきることなく、生き延びることができました。本当にありがとうございました』」
愛のこもった作品を作った人に、言葉の達人が愛をこめて話を聞く。読み進めるにつれて、「よくわからないけど、あきらかにすごい!」って、なんだか元気が湧いてきました。
[出版社のサイトへ]
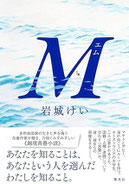
M
岩城けい(集英社)
米原万里さんの『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』やブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を挙げようかと思ったのですが、読んだのがずいぶん前なので、こちらにしました。マサト三部作『Masato』『Matt』『M』の最終章です。
12歳で親の都合によりオーストラリアに移住し、現地で育っていく「マサト」がついに大学生になり、同じく親の都合でアルメニアから来ている女の子と出会います。マサトが大人になっているので、日本人としてのアイデンティティやコンプレックスが複雑に描かれ、考えさせられます。
同じ系統なら、温又柔さんなどもいいかもです。簡単にグローバルとか多様性って言うけど、多様な人たちがうまく共生する方法を探ることは深くて難しいですね。もしかしたら隣に座っている人が、こんなことを考えているのかもしれないって思いました。
[出版社のサイトへ]

須賀敦子の手紙 1975-1997 友人への55通
須賀敦子(つるとはな)
著者の須賀敦子さんは、イタリア文学を翻訳したり、エッセイを書いたりされた方。もしかしたら教科書で「クレールという女」を読んだ人がいるかもしれないですね。
スマートフォンで簡単にテキストを送れるようになり、手紙文化が失われつつあるのですが、この本を読めば、誰かに手紙を書きたくなります。ちょっと渋めのインクのペン(太字)を買いたくなります。
エッセイで出会う須賀敦子さんは、知的でキリリとした方ですが、親友「おすまさん」に送った手紙の中の須賀さんは、かなりお茶目でかわいい「あつこ」さんです。離れて暮らす親友に、この本をプレゼントしました。
[出版社のサイトへ]

バッタを倒しにアフリカへ
前野ウルド浩太郎(光文社新書)
「どういうタイトル?」と思って手に取ると、仮面ライダーみたいなバッタ人間(失礼、恐らく前野さん)が捕虫網を構えたイラスト。しかしこの人はどうやら歴とした昆虫学者で、お笑い芸人みたいな「ウルド」も、アフリカの現地の人と仲良くなって授けられた名前らしい。
「トガッた発想を」とか「好きこそものの上手なれ」とか、簡単に言うけど、「研究する」っていうのは大変なことなんだな、でもめっちゃ楽しそうやん!と思いながら読んだことを覚えています。京大の白眉研究員に選ばれるための面接で、面接官が言ったセリフに一番感動しました!
川上和人『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ』もおススメ。どちらも、内容だけでなく読み物として面白く、笑いながら読めます。
[出版社のサイトへ]

石原先生 一問一答
Q1.先生の好きな本のジャンルは?
日本の小説。高校時代は宮本輝をよく読んでいました。「流転の海」シリーズが完結したので、数年前に読みなおしましたが、人生のどちらかというと暗い部分も描きつつ、登場人物たちが人間として真っ当で、高校生に勧めたいなと思いました。
Q2. 高校時代に読んで印象に残っている本は?
尾崎紅葉『金色夜叉』。3年の時に授業で「舞姫」を読んで、「え、私、こんなの読めるんだ」と思って手に取ったらやめられず、受験勉強もそっちのけ。「とにかく読み終えよう」と思い、自習時間もずっと読んでいました。大学に入って、一人だけ同じ体験をした人に出会いました(笑)
Q3.好きな漫画・アニメは?
「海街diary」吉田秋生、「君に届け」椎名軽穂、「六三四の剣」村上もとか、「宇宙兄弟」小山宙哉、「かくかくしかじか」東村アキコ、「コウノドリ」鈴ノ木ユウ、「リアル」井上雄彦