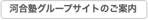高校の図書館司書・先生が推薦!本の魅力 <3>
地方、農業、経済、そしてヤングケアラー…。自分の身の回りを学び、新しい働き方を考えよう
早稲田大阪高等学校(大阪府)(旧早稲田摂陵高等学校) 米田謙三先生
★全国の多くの地域は、いわゆる「地方」になります。都会ではなくその場をどう生活の場として活性化させるかは大事な問題です。そういう視点も踏まえつつ、地域再生や人口減少、そして農業や経済全体も考えていきたいです。

地域再生の失敗学
飯田泰之、木下斉 ほか(光文社新書)
地域活性化の取り組みが失敗する原因と、成功するための具体的な方法を分析。実際の事例を通じて、まちづくりのリアルを学びたい高校生におすすめ。
[出版社のサイトへ]

まちづくりを学ぶ 地域再生の見取り図
石原武政、西村幸夫 (有斐閣ブックス)
まちづくりの基本理念から実際の取り組み事例までを網羅した入門書。 まちづくりに興味があり、将来的に都市計画や地方創生に関わりたい人に。
[出版社のサイトへ]

タガヤセ!日本 「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます
白石優生(河出書房新社)
農林水産省で働く著者が、日本の農業と食の未来、そして農林水産省の仕事について熱く語ります。農業や食に興味がある高校生におすすめで、日本の農業の魅力や課題を知ることができます。
[出版社のサイトへ]

21世紀の資本
トマ・ピケティ 山形浩生ほか:訳(みすず書房)
資本主義経済における所得格差の歴史とその原因をデータに基づいて分析しています。 現代の経済問題や格差に関心のある高校生におすすめです。
[出版社のサイトへ]
★身の回りといえば家族のあり方も変わりつつあります。

ヤングケアラーってなんだろう
澁谷智子(ちくまプリマー新書)
家族の世話や家事を行う子どもたちを指す「ヤングケアラー」について、その状況や支援の取り組みを紹介しています。ヤングケアラーの基本的な理解を深めたい高校生に。
[出版社のサイトへ]
★どんな課題にも関わり、大事になってくるのは、情報やデータの世界。DX、AI、ICTなど情報系技術の動向も知っておけるといいでしょう。知るきっかけになる3冊をあげました。

AI vs. 教科書が読めない子どもたち
新井紀子(東洋経済新報社)
AIが東大入試を突破できるかという実験「東ロボくんプロジェクト」の結果から、AIの限界と人間の役割について考える。AIは万能?人間にしかできないことは何か? AIの進化と教育の関係について学べる1冊。
[出版社のサイトへ]

シンギュラリティは近い
レイ・カーツワイル(NHK出版)
AIが人間の知能を超えるとされる「シンギュラリティ(技術的特異点)」について、未来予測を交えて解説。「AIが発展し続けたら、未来はどうなる?」 未来のテクノロジーに興味がある人向けの1冊。
[出版社のサイトへ]

ゼロから作るDeep Learning
斎藤康毅(オライリー・ジャパン)
Pythonを使いながら、ニューラルネットワークの基礎をゼロから学べる。実際のプログラミングを通じて深層学習の仕組みを理解できる。「AIを自分で作ってみたい!」 プログラミングに興味がある人向けの1冊。
[出版社のサイトへ]

米田先生 一問一答
Q1.先生の好きな本のジャンルは?
科学・テクノロジー(AI、宇宙、未来予測など)。イチオシは、『宇宙を編む: はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる』(井上榛香)、『時間は存在しない』(カルロ・ロヴェッリ)。
Q2.最近読んだ本で、おすすめしたい本は?
『スペース・バロンズ:イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、そして新宇宙時代の覇者たち』(クリスチャン・ダヴェンポート)、『AI 2041: 人工知能が変える20年後の未来』(カイフー・リー & チェン・チウファン)