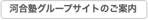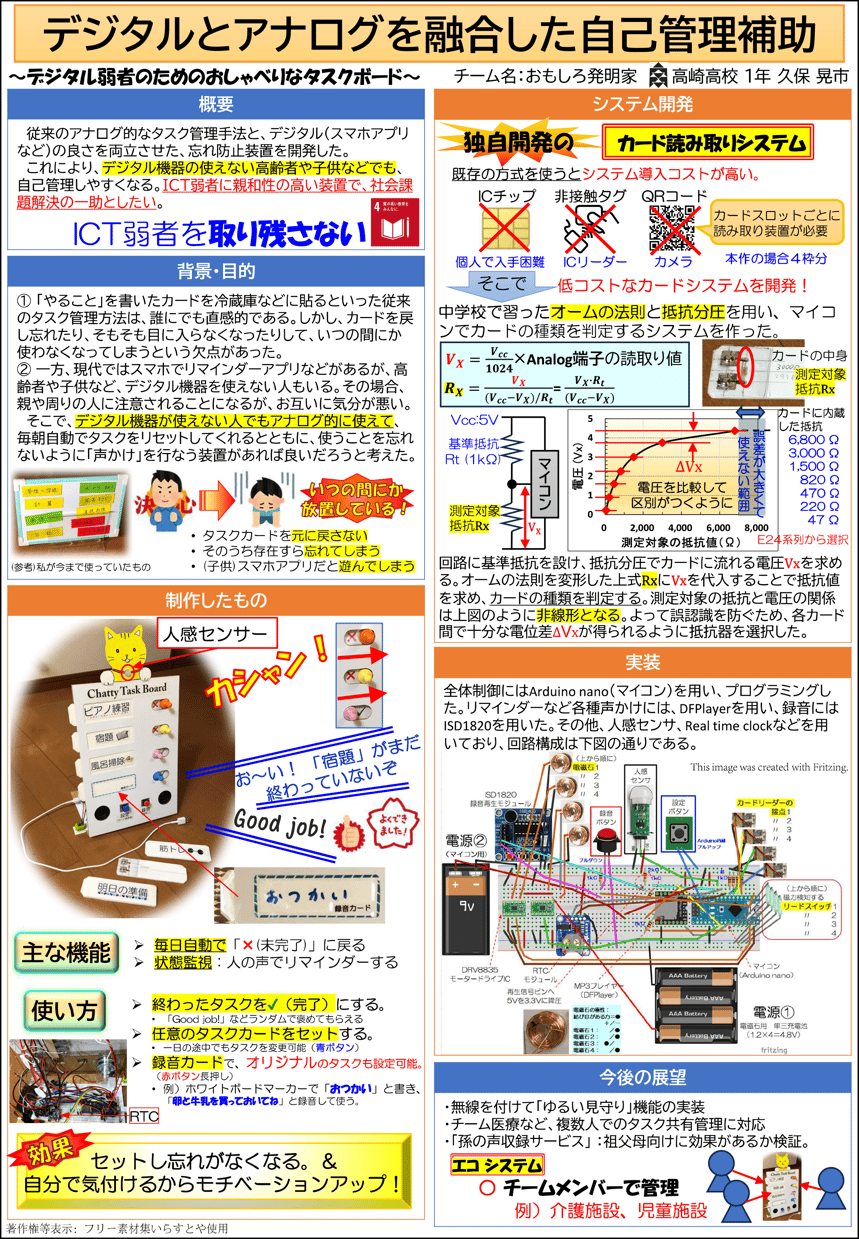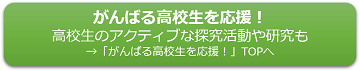第87回情報処理学会全国大会 第7回中高生情報学研究コンテスト
デジタル弱者にもデジタルの恩恵を! アナログ的に使えるおしゃべりなタスクボード
群馬県立高崎高校
チーム名:おもしろ発明家
久保晃市くん(1年生)
(2025年3月取材)
デジタルとアナログを融合した自己管理補助
※クリックすると拡大します
◆今回発表した研究を始めた理由や経緯を教えてください。
「やること」を書いたカードを冷蔵庫などに貼るといった従来のタスク管理方法は、誰にでも直感的です。しかし、カードを戻し忘れたり、そもそも目に入らなくなったりして、いつの間にか使わなくなってしまうという欠点がありました。
一方、現代ではスマホでリマインダーアプリなどがありますが、高齢者や子供など、デジタル機器を使えない人もいます。その場合、親や周りの人に注意されることになりますが、お互いに気分が悪いです。
そこで、デジタル機器が使えない人でもアナログ的に使えて、毎朝自動でタスクをリセットしてくれるとともに、使うことを忘れないように「声かけ」を行う装置があれば良いだろうと考えました。
◆今回の研究にかかった時間はどのくらいですか。
1回目のプロトタイプの作成には約4か月かかりました。現在、ユーザーテストに耐えうるレベルに仕上げるため、改良を進めているところです。
◆「ココは工夫した!」「ココを見てほしい」という点を教えてください。
タスクカードの読み取りの際に、既存の方法(ICチップ、非接触タグ、QRコードなど)は、1対多の場合に有用です。しかし、本製品のように、カードスロットごとに読み取り装置が必要となる場合、コストが高くなってしまいます。そこで、低コストなカードリーダーを開発しました。
これは、抵抗分圧とオームの法則を用いて、マイコンでカードの種類を判別するものです。その際、測定対象の抵抗と電圧の関係が非線形であるため、条件によってはエラーを起こします。そのため、各カード間で十分な電位差が得られ、かつ、一般的な抵抗器の仕様とも整合する仕様を定めました。
また、タスクつまみがマグネットであるため、電磁石でタスクつまみの位置を戻せるとともに、磁力を検知することで、タスクの状態も監視できるようになりました。
◆今後「こんなものを作ってみたい!」「こんな研究をしてみたい」と思うことがあれば教えてください。
まずは、このタスクボードをさらにブラッシュアップして、実用化までもっていきたいです。具体的には、タスクごとにリセット時間を設定したり、無線につないで見守りする機能を追加するなどを考えています。
※久保くんの発表は、中高生研究賞奨励賞・初等中等教育委員会 委員長賞を受賞しました。
→他の記事も読もう